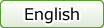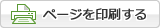重要資料_静岡県がんセンター基本構想
(P266-270)
『静岡県がんセンター基本構想(1996年3月策定)』
“最新で適切ながん診療
患者の視点の尊重
がん情報ネットワークの構築”
![]() はじめに
はじめに
本格的な高齢社会を目前に控え、県民の疾病構造が感染症から成人病へと変化している中で、現在、県民の4人に1人ががんで亡くなり、今後もがんの罹患者と死亡者の増加が予測されるなど憂慮すべき事態を迎えており、がんの克服は県民的課題となっている。
一方、がんを不治の病とする誤った考え方は今日も根強いものがあるが、最近のがんの診断・治療における技術の進歩などに伴う治療成績の改善は目覚ましく、がんの高度専門医療機関においては、今や2人に1人の命が救われるまでになっている。
このため、静岡県では県民的課題であるがんの克服を目指し、医療機関の地域バランスも考慮して、県東部地域に静岡県がんセンター(仮称)を設置することを「新世紀創造計画」の重要施策と位置付けている。
今回、患者の視点を尊重した最新で適切ながん診療を実践し、県民の理解を求めつつ、県民のためのがん対策を推進して、県民の健康に重大な影響のあるがんから、1人でも多くの命を守るため、我が国でもトップレベルのがん高度専門医療機関を目指した、静岡県がんセンター基本構想をまとめた。
![]() 1 基本理念
1 基本理念
静岡県がんセンターは、21世紀のあるべき医療を先取りし、静岡県らしい特徴と魅力を有する、患者・家族の立場に立った医療を提供するとともに、国際的にも情報発信できるがん対策の中枢機能を持った、我が国でもトップレベルのがんセンターを目指す。
このためには、県民の命をまかせられる優れた医療スタッフを全国から招へいするとともに、先進的医療機器の整備や患者の療養環境に適した施設整備を行い、がんの研究・予防・診断・治療・リハビリ・緩和ケアまでの一貫した体制を構築して、国内外のがん高度専門医療機関との組織的連携を図り、最新の医療技術を駆使した適切ながん診療の実践が必要である。
また、患者や家族の痛み・苦しみ・悩みなどに対応できる、患者の視点を尊重したがん診療を推進する。
さらに、県民のためのがん対策の中枢機能を果たすことが重要である。静岡県がんセンターでは、国立がんセンターが推進しているがん診療総合支援システムに参加して、がん情報ネットワークを構築し、国内外のがん高度専門医療機関及び県内の医療機関や保健所、保健センターなどとの一層密接な連携を図り、県民に対する啓もう活動や相談業務などを充実させるとともに、県内で働く医療従事者を対象に、最新のがん診療技術の研修・教育活動を行う。
また、民間活力などを導入して官民共同プロジェクトなどにも取り組むことが期待される。
以上により、静岡県がんセンターの整備に当たっては、次の3点を基本理念とする。
第一は、最新で適切ながん診療の実践
第二は、患者の視点を尊重したがん診療の推進
第三は、がん情報ネットワークなど、がん対策の中枢機能の構築
![]() 2 がん診療・研究機能
2 がん診療・研究機能
静岡県がんセンターでは、21世紀に必要とされる医療を念頭においた診療・研究体制を整備し、我が国有数のがん診療技術を持つことが最も重要である。
このためには、各診療部門や研究部門、管理運営部門に優れた人材を配置することが求められる。また、学閥を排し、国立がんセンターや各県のがんセンターの協力を得て、優れた人材を招へいするとともに、さらなる技術の向上を目指し、最新技術の開発あるいは導入に努め、全国各地のがん高度専門医療機関との積極的な人的交流を深めていく必要がある。
一方、病院機能については、診断・治療・リハビリ・緩和ケアの機能を有するとともに、がん診療に役立つ新しい診療機器を整備することが必須である。また、がん患者の様々な病態に対応し、かつ、災害緊急時の対応も可能な総合診療部門、最新の画像診断技術や血液診断法などを駆使した新しい理論に基づくがん診療部門、遺伝子診断や遺伝子治療を目指す遺伝子診療部門、がん患者との対話を重視した薬剤部門、充実した緩和ケア部門、在宅ケアを推進する在宅ケア部門などの設置が必要である。
なお、最新の画像診断装置(PET注など)や粒子線治療装置についても、その導入を検討することが必要である。
さらに、我が国有数のがん高度専門医療機関を運営し、同時に、県民を対象としたきめ細やかながん対策の中枢機能としての役割を果たしていくためには、高度な研究機能を持つことが必要である。
特に、病院機能を密接にした臨床支援研究機能、がん診療技術開発機能、がん登録機能などを中心に、東京や大阪のような大都市圏とは異なる地域に密着した、がん高度専門医療機関としての特色ある研究項目の設定が必要である。(注)PET:ポジトロンCT(コンピューター断層撮影の一種)
![]() 3 患者の視点を尊重した診療
3 患者の視点を尊重した診療
いかに優れた診療技術を持っていても、医療の現場で患者の視点が軽んじられ、患者にとっての“安心感・快適さ”と、医療従事者の“誠実さ・優しさ”が欠如していれば、県民から慕われるがんの高度専門医療機関とはなり得ない。従って、様々な角度から患者の視点を尊重したがん診療を計画的、かつ着実に進める仕組みを考える必要がある。
同時に、患者・家族との交流を図り得る談話室など、快適な療養環境を有した病院の施設整備に努めるとともに、自然環境との調和に十分配慮することが重要である。
また、女性の意見などを施設の整備に十分反映させることに努め、乳がんや婦人科系統のがんを中心とした、女性専用の病棟なども検討するなど、女性に対する配慮が必要である。
がん患者の増加に伴い、自らががんに悩み、また家族の病気を心配するという状況が多く見られるようになることが予測されるため、県民を対象として、患者の視点に立ったがん情報の普及・提供を行う必要がある。
このため、病院を訪れる患者のみならず、県民のニーズに応えられるよう、がん情報ネットワークの中で、電話・ファックス・パソコン通信などを利用したがん医療相談システムを整備する必要がある。
一方、このようないわば、“物質的アメニティ ”とともに、患者やその家族の“精神的アメニティ ”を追求することの必要性が今後増していくものと思われる。現在、がんの告知やインフォームドコンセント(説明と同意)の重要性が指摘されているが、患者の不安を受け止める体制が整ってこそ、はじめて患者の視点を尊重した、真のがん告知やインフォームドコンセントが実現できる。
このため、優れた医療技術を有する信頼に足る医療スタッフに加えて、十分な医療上の対話、相談が可能なシステムの構築も重要である。
![]() 4 がん対策の中枢機能
4 がん対策の中枢機能
静岡県がんセンターは、県民のためのがん対策の中枢機能を果たすことが求められる。
静岡県がんセンターから、がんの診療・研究に関わる情報を世界や国内のがん高度専門医療機関に発信し、あるいはそれらの機関から情報を収集したりするシステムの構築は、最新のがん診療を行う上で必須のものである。また、患者のプライバシーを重視して、新しい薬剤やその副作用に関する情報、個々の症例についての紹介、他機関とのテレビ会議など、このようなシステムの活用が今後とも最新のがん関連情報の集積や診療に有益となり得る。
このためには、我が国の代表的ながんセンターや世界のがん高度専門医療機関を結ぶ“がん高度専門医療機関ネットワーク”の構築を目指す。一方、県内の医療機関や保健所、保健センターと協力して、がん登録などがんに関する情報を整備するとともに、がんの予防や治療に必要な情報を提供する。また、患者の診療に当たっては、画像診断や病理診断の援助機能を持つ“静岡がん診療ネットワーク”、さらには電話やパソコン通信で直接県民との対話を可能とする“静岡がん相談ネットワーク”などを中枢機能とする“がん情報ネットワーク”の構築に努める。
また、このような情報システムとは別に、がん診療従事者を中心とした様々な研修・教育活動を行い、県内のがん診療レベルの向上に努めることが重要である。さらに、県内医療機関や保健所、保健センターなどとの一層の連携の下に、がん予防対策の積極的な展開を図ることも必要である。
![]() 5 施設規模、立地条件、優れた経営効率
5 施設規模、立地条件、優れた経営効率
施設規模としては、概ね500床以上が適当である。最終的には、がん患者の受療動向やマーケティング・リサーチなどを参考とし、さらに経営効率も考慮して決定することが必要である。
また、会議室、研修室、相談室、ボランティア室、カンファレンス室、器材室、備蓄室などの施設整備は、10 〜 15年先の需要にも耐え得る余裕のあるスペースが確保できるように配慮する必要がある。
立地条件としては、県中部・西部地域に比べて、高度医療機関の配置が手薄な東部地域の医療を向上させ、将来の発展とともに、この地域を高度先進医療の拠点へと変貌させるのに最適な場所とする必要がある。
そのため、病院施設の視点からは、診療と研究の両機能が発揮できる十分な敷地面積(約 10ha以上)が容易に確保できることが必須である。また、医療スタッフなど優れた人材を求める視点からは、医療従事者の研究・研修活動などの現状や、国内の指導的ながん高度医療機関との連携を図る上からも優れた人材の確保が行いやすいところであること。患者・家族の視点からは、通院に便利な交通の要衝であり、県内各地から容易にアクセスできるインターチェンジや新幹線などの鉄道駅に至近距離であること。さらに、富士山や駿河湾を望める良好な療養環境であること、などが必須の条件であり、近隣の高度医療機関や先進的研究機関などとの連携が図られ、がん医療の相乗効果が期待できるところも参考とすべきである。
経営面では、従来の病院機能を見直し、自動化や外部委託の積極的な導入、看護体制の開発などを進め、その効率化を図る。さらには、SPD(中央物品供給管理センター)の導入や県立病院間での物品の共同購入を行うなど、優れた経営効率の追求が必要である。また、がんセンターの機能が県民に理解されるような広報活動を行う部門の設置も必要である。
研究面では、病院機能との密接な関係を図るとともに、財団法人などを活用した研究・臨床支援体制の整備も検討する必要がある。同時に、事務管理部門を充実させることにより、医療従事者が診療に専念できる体制を実現させる必要がある。
さらに、運営面では、紹介予約制の導入による県内医療機関との一層の連携、優れた医療スタッフ・研究者を確保するための公募制、任期制などといった、新しい発想・視点からの取り組みも考慮する必要がある。
また、地域社会との連携においては、静岡県がんセンターを中核に据え、民間活力などを導入して、県東部地域が全国有数の“医療モデル地域”となるよう努めることが重要である。
![]() おわりに
おわりに
今回、県民の健康に重大な影響のあるがんの克服を目指し、全国に誇れるような、県民のためのがんセンターが建設できるよう様々な議論を重ね、この基本構想をまとめた。
本年、奇しくも静岡県が生誕120周年を迎える時に当たり、これらの提言が生かされ、21世紀までの残された期間に県民のニーズに応え得る、がん高度専門医療機関の整備を進める。
(参考)
検討経緯
平成7年10月24日 第1回委員会開催
・本県のがんの現状と課題
・基本構想に盛り込む事項
平成7年11月27日 第2回委員会開催
・米国がん診療病院等調査報告
・基本構想に盛り込む事項
平成8年1月24日 第3回委員会開催
・国立がんセンター東病院視察
・基本構想スケルトン
・基本構想原案
平成8年2月6日 第4回委員会開催
・静岡県がんセンター基本構想案
|
静岡県がんセンター基本構想検討委員会委員名簿(敬称略:五十音順) 会長 大石益光 静岡県総合計画審議会長、㈱静岡新聞社社長 事務局 保健衛生部衛生企画課 |