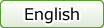初めての受診 - 医療機関や医師の選択 -
Q.「これから治療を受けるためにはどの病院や医師がよいか選択に悩んだ。」
病院を選ぶ際には、2つのポイントがあります。
(1)自分がどのような医療機関にかかりたいのか
(2)交通の便や経済面への負担はどうか
がんは慢性疾患ともいわれるので、長い経過を見据えて考えましょう。
自分はどのような医療機関にかかりたいか
現在、日本人が一生のうち、がんと診断される確率は2人に1人と言われています。
厚生労働省は、どこにいても、誰でも安心してがんの治療が受けられるように(がん医療の均てん化)、『がん診療連携拠点病院』を設置しています。国立がん研究センターがん情報サービスの用語集によると、がん診療連携拠点病院は、『専門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携協力体制の整備、患者・住民への相談支援や情報提供などの役割を担う病院として、国が定める指定要件を踏まえて都道府県知事が推薦したものについて、厚生労働大臣が適当と認め、指定した病院です。がん診療連携拠点病院には、各都道府県で中心的役割を果たす「都道府県がん診療連携拠点病院」と、都道府県内の各地域で中心的役割を果たす「地域がん診療連携拠点病院」があります。』と説明されています。
これらの病院は、がんの診断や治療をしていくための条件を満たしているかなど、よく検討され審査されて、指定を受けます。がん診療連携拠点病院の情報は、国立がん研究センターがん情報サービスの『がん診療連携拠点病院を探す』で、確認できます。
どのようながんを取り扱っているか、どのような治療を行っているか、どのような専門医や専門職がいるかなど具体的に概要をみることができるので、病院を決めるとき、参考になると思います。
しかし、がんの治療は、がんの専門病院でないと受けられないということではありません。試験的治療などの場合には、がん専門病院や大学病院が適していることもありますが、一般の病院でもがんの治療は行われています。
また、がん専門病院や大学病院では、一般病院では治療が難しい患者さんも多いため、予約待ちの期間があったり、外来診療も待ち時間が長く1日がかりになってしまったり、入院待機期間が長くなってしまいがちです。一方で、できるだけ自宅から近い病院にかかりたい、今までかかったことがあり、信頼している先生に診てもらいたいと考える人もいるはずです。
つまり、自分がどのような基準で病院を選ぶかで、検討する医療機関も異なってきます。
交通の便や経済的な負担面も検討する
がんは慢性疾患といわれ、長い経過を見据えて検討する必要があります。たとえば、『手術をすれば終わり』ということではなく、手術を受けてもその後定期的に通院し必要な検査や診察を受けていく必要がありますし、治療が終了しても再び治療が必要になる場合もあります。手術と薬物療法(抗がん薬治療)を組み合わせたり、薬物療法と放射線療法を組み合わせたりする『集学的治療』も行われるようになってきています。
また、現在、技術の進歩や医療制度の変化などから、入院期間の短縮化がすすみ、薬物療法(抗がん薬治療)も多くは、外来で通院しながら治療を行えるようになっています。放射線治療などは決められた期間、放射線治療を受けるために毎日通う必要があります。
通院をしている間には、体調があまりよくないときもあります。治療で頻回に通院しなければいけないときは、通院の時間が長くなることで疲労が強くなることもあります。家事や育児、仕事をしながら、通院や通院治療をしなければいけないときは、時間の調整や体への負担をできるだけ減らすことを考えなければいけません。
その他には、ご家族が車で送り迎えしてくれる場合でも長期間になると、お互いにとって負担になってしまったり、どうしてもご家族の手があかなかったりする場合も起こりえます。
入院の際も、ご自宅の近くであれば、ご家族が仕事帰りなどに顔を出されたり、用事があってもお互いあまり負担に感じずにお願いができたりします。しかし、遠方ですと、ご家族も時間がとれないと面会に行けないし、面会に行く際の交通費やガソリン代もかかります。
高齢の方ですと、自分の住んでいる所と全く異なる環境におかれることが、大変なストレスになることもあります。
通院時の交通費も、長期間になると負担感が増します。あらかじめ交通費を算出し、経済的な負担にならないか、確認しておきましょう。
通院の際、自家用車など車を使われる方もいらっしゃいますが、公共交通機関(バスや電車等)を利用すると、医療費控除の対象になりますので、公共交通機関(バスや電車等)を利用して通院できる病院を選ぶのもよいかもしれません。タクシー代(やむを得ない場合をのぞく)、自家用車のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象外になります。
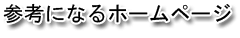
(1)国立がん研究センター『がん情報サービス』
https://ganjoho.jp/public/index.html
『がん情報サービス』は、国立がん研究センターが運営するがんに関するさまざまな情報を提供するサイトです。がんの部位や診断名による解説、診断や治療、生活や療養に関する情報、制度やサービスに関する情報などの他、地域のがん情報では、都道府県別のがんに関連した情報へのリンクなどがあります。
(2)国立がん研究センター『がん情報サービス』:相談先・病院を探す
https://hospdb.ganjoho.jp/
成人や小児の相談先・病院一覧(がん診療連携拠点病院、小児がん拠点病院)が掲載されています。
(3)日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医
https://www.jsmo.or.jp/
日本臨床腫瘍学会のホームページです。『一般の皆さまへ』に、『がん薬物療法専門医について』の説明や『専門医名簿』のリスト(PDF)を確認できます。
(4)日本放射線腫瘍学会 放射線治療専門医
https://www.jastro.or.jp/
日本放射線腫瘍学会のホームページです。『一般の方』のページに『放射線治療Q&A』、『市民公開講座』、『放射線治療を知るパンフレット』など放射線治療についての参考資料があります。また、『放射線治療専門医リスト』は、都道府県ごとに確認できます。
(5)日本乳癌学会:乳腺専門医とガイドライン
https://www.jbcs.gr.jp/
日本乳癌学会のホームページです。トップページの[市民のみなさまに知ってほしい情報]から、患者さんやご家族、一般の方々向けの乳がん診療ガイドラインや乳癌学会専門医一覧など、さまざまな情報が掲載されています。
Q.「担当医の経験、能力が判断できず、安心してまかせられるのか不安だった。」
信頼できる医師というのは、その人(患者さん)自身の価値基準が入ってきます。自分は、医師に何を求めるのか、責任感がある、人柄がよい、専門的知識・技術を身につけている、説明を十分に行ってくれる、話しやすいなどいろいろあると思います。
このなかで、専門的知識や技術を身につけているという基準は、1つには学会などで認定している専門医資格を参考にすることができます。また、医療機関のホームページに、病院の方針(理念)、診療科の案内、設備のほか、各診療科の詳細な情報や治療実績等が載っていることがあります。
医師には自分の体を預けるわけですから、特に、医師との関係性が気になると思います。ただし、責任感があるとか話しやすいというのは、客観的な指標はなく、判断基準としては難しいかもしれません。
また、医師も人間ですから、関係性が築きやすい場合もあれば、難しい場合もあります。そのようなときは、どちらか片方の働きかけが有効に働くことがあります。また、周囲の人が助けになってうまくいく場合も多くみられます。医師との信頼関係は、お互いが築きあげていくものだと思います。
(更新日:2019年2月25日)
ご意見・ご感想
よりよい情報提供を行うために、ご意見やご感想をお寄せください。
いただいた評価やご意見・ご感想は、今後、このコンテンツ(情報のなかみ)に役立たせていただきます。
なお、個別の回答やご相談は、仕組み上できかねますので、お困りごとやご相談がある方は、下記「がん相談支援センター」をご利用ください。
【がん相談支援センター】
お困りごとやご相談がある方は、●静岡県内の方は、
静岡がんセンター「よろず相談」
もしくは、静岡県内のお近くのがん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター」
●静岡県外の方は、
お近くのがん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター」
にご相談ください。
外部サイトの役立つリンク集
国立がん研究センター『がん情報サービス』
https://ganjoho.jp