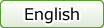入院についての説明不足
入院する際、入院期間は何日くらいになるか、何人部屋にするか、支払いがどのくらいになるか悩んだ。
入院期間の長さと必要性について今ひとつ明確な説明がなく、釈然としなかった。
助言
自分の助言集をつくる
EPUB形式でダウンロード 印刷用表示
印刷用表示
【ポイント】
入院について不明な点があれば、確認が必要です。誰に何をどのように確認すればよいのか整理してから確認しましょう。
【治療に関する説明、入院期間など】
入院期間は、治療の種類、病状、治療によっても異なりますが、大体この治療であれば、このくらいという目安はあります。現在では、どこの医療機関でも、入院期間は短縮されてきていますが、医療機関によっても、入院期間には少し差はあります。
入院が決まった際に、入院期間がどのくらいか、およそのところを担当医に確認してみましょう。また、それ以外にも、入院に際し、疑問な点、確認しておきたい点は、メモなどに箇条書きであらかじめ整理しておき、きちんと確認しておきましょう。なお、入院に際しての注意事項や準備物などは、看護師から説明がある場合もあります。
【入院予定日】
小さなお子さんがいらっしゃったり、お仕事の引継ぎをしたり、介護が必要な高齢者がいらっしゃるなどさまざまな理由で、入院予定日を知りたい方は多いと思います。けれども、入院患者さんの状況により、予定より退院が延びたり、緊急入院が入ったりということがあり、○月○日に必ず入院とはっきりすることはあまりないと思います。一時的に預かってもらう施設を利用したりすることを考えるときには、その点、施設担当者にも事情を伝えて調整が可能か確認しましょう。
【入院の費用や支払い】
入院前に、ご自分の入院費用が全体としてだいたいどのくらいかかるのか、医師あるいは会計事務に確認してみましょう。どのくらいお金を準備しておいたらよいか把握しておくことは、安心感につながります。また、クレジットカードが使えるかなど医療費の支払い方法も確認しておいた方がよいでしょう。
入院費は、治療や薬代以外に、入院基本料(平均在院日数や看護師配置より異なります)、食事代などを合わせたものになります。
がんの治療や検査にかかる医療費は、予想以上に高額で、経済的に悩んでしまうことがあると思います。このように高額な医療費による経済的負担を軽減するために、高額療養費制度(対象となるのは、公的医療保険が適用される医療費)があります。ただし、高額療養費制度には、差額ベッド代、食事代、診断書等の書類作成費用、保険適用外の治療費などは含まれないのでご注意ください。
高額療養費制度などの制度は、わかりにくいと感じる方もいらっしゃると思います。静岡がんセンターのホームページで公開している小冊子『医療費のしくみ』は、図表などでわかりやすく詳細な説明がありますので、ご参照ください。PDF形式でダウンロードできます。
◎ 『認定証』の申請
『高額療養費制度』は、医療機関等で支払った医療費(差額ベッド代や食事代などは別途必要になります)が、月の初めから終わりまでの1か月で一定の額(自己負担限度額)を超えた場合に、保険者に申請することで(多くの健康保険組合は、自動的に高額療養費が支給されます)、その超えた金額を支給する制度になります。
医療費は年齢や収入に応じて1カ月に支払う自己負担限度額が定められています。
医療費が高額になりそうなときには、あらかじめ所得区分の『認定証』の交付を受けて医療機関の窓口で提示することで、入院、外来診療ともに窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
70歳以上の一般区分の方は認定証の申請は不要であり、医療機関の窓口で自動的に自己負担限度額までの請求になります。また、3割負担の方で現役並みⅢの方は、一般区分同様認定証はなく、窓口で自動的に自己負担限度額までの請求になります。ただし、保険証のみでは現役並みⅢか否かが判断できません。その為3割負担の方は、健康保険の窓口にて認定証の申請についてご確認ください。
注意)国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は認定証の発行がされない場合があります。
『認定証』の申請をせずにいったん窓口で支払いをした場合も、後日、保険者に申請をして自己負担限度額を超えた金額の払い戻しを受けることができます。ただし、高額療養費を申請して支給されるまでには、少なくとも3ヶ月程度かかります。1ヶ月に1つの医療機関での支払いが高額になる可能性がある場合は、『認定証』をあらかじめ申請しておきましょう。マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)の手続きをされている場合、マイナンバーカードを利用できる医療機関窓口では、限度額適用認定証がなくても、限度額を超える支払いは免除されます。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局では、マイナンバーカードだけではなく、通常の健康保険証の記号番号等によりオンライン( オンライン資格確認等システム)で資格確認をすることが可能になります。これにより、患者さんは限度額定期用認定証を持参しなくても限度額の区分が医療機関に伝わります。ただし患者さん側に限度額の区分を証明する書類はありませんので、オンライン資格認証をした場合にはご自身の限度額の区分を確認しておいたほうがよいでしょう。
おかかりの医療機関等が「オンライン資格確認等システム」を導入しているかどうかは、医療機関等の支払い窓口、あるいは厚生労働省のマイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)等でご確認ください。
払い戻しの対象になる方は、高額療養費として事前に登録されている高額療養費の口座に後日払い戻します。
『認定証』の申請の際には保険証(資格確認書)のほか、印鑑等が必要になることもあるので、あらかじめご自身が加入している保険者に電話等で確認するようにしてください。
<入院費に関するポイント>
◎ 差額ベッド代がかかるのか、利用する場合は費用を確認
◎ 請求書はいつ頃くるか、いつ頃までに支払うのか、支払い方法(カードは利用できるかなど)を確認
◎ 退院時は支払い前に概算金額を確認し、費用を準備しておく
【加入している民間保険の確認】
民間保険に加入している場合は、保険証書や問い合わせ窓口などを確認しておきましょう。治療方針が決まったら、保証内容、手続き方法などを保険担当者に問い合わせましょう。
契約されている保険によっては、診断書が不要な簡易請求(医療機関で発行される診療明細書、領収証及び治療状況報告書等で請求)が可能な場合や、他の生命保険会社に提出する診断書のコピーでの対応ができる場合がありますので、保険請求手続きをする前に確認をしましょう。
(最終更新日 2025年7月25日)
関連する情報
ご意見・ご感想
よりよい情報提供を行うために、ご意見やご感想をお寄せください。
いただいた評価やご意見・ご感想は、今後、このコンテンツ(情報のなかみ)に役立たせていただきます。
なお、個別の回答やご相談は、仕組み上できかねますので、お困りごとやご相談がある方は、下記「がん相談支援センター」をご利用ください。
【がん相談支援センター】
お困りごとやご相談がある方は、●静岡県内の方は、
静岡がんセンター「よろず相談」
もしくは、静岡県内のお近くのがん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター」
●静岡県外の方は、
お近くのがん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター」
にご相談ください。
がん体験者の悩みQ&A
がん体験者の悩みQ&A
- 悩みと助言
- 静岡県 医療と暮らしの情報
- 発行した冊子
- 電子書籍
- がん体験者の悩みを知る
- このサイトについて