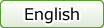悩み
年金生活なので高額な治療代に悩んでいる。そのうえ、がんの治療だけではなく、眼科や高血圧の治療、歯科などの医療費もかかり、大変である。
助言
自分の助言集をつくる
EPUB形式でダウンロード 印刷用表示
印刷用表示
【ソーシャルワーカーに相談してみましょう】
年金生活で、がん以外の病気の治療費もたくさんかかっている、という状況は、経済的にとてもつらいものだと思います。
経済的な悩みへの対処を考えるときには、あなたが置かれている状況を個別に検討していく必要があります。治療費で困っている方の手助けとなる制度はいろいろありますが、あなたの状況に適した制度を選んで活用するためには、専門的な知識が必要になります。
治療費に関する相談を含め、生活全般の相談に対応する専門職として、ソーシャルワーカーがいます。おかかりの病院が総合病院や大学病院等であれば医療相談室や患者支援センターなどにソーシャルワーカーが配置されていることがほとんどです。まずは受付や医療スタッフ、相談室でたずねてください。
おかかりの病院にソーシャルワーカーがいない場合、お住まいの地域の近くにあるがん診療連携拠点病院のがん相談支援センターのソーシャルワーカーに相談することも方法です。がん相談支援センターについては下記のホームページで調べてみてください。
お悩みの文面だけではお伝えできることは限られていますが、参考までに少し具体的な情報もお伝えしておきます。
お悩みの状況であれば、一般的にはまず高額療養費制度の活用を検討することになると思われます。
この制度は、保険診療の対象となる医療費について、1か月の自己負担を一定の金額におさえることができる制度です。制度の概要については、静岡がんセンターホームページの『冊子・電子書籍・動画』ページにある小冊子 学びの広場シリーズ 暮らし編「医療費のしくみ」(冊子PDF版)をご覧ください。
また、あらかじめ限度額適用認定証などの所得区分の『認定証』を保険者に交付申請しておき、医療機関の窓口で提示することで、入院診療・外来診療ともにあらかじめ支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
治療(外来・入院)に際し、高額な医療費が予定されている場合は限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準限度額認定証)を申請し、入手しておきましょう。
・70歳未満、70歳以上の方で住民税非課税世帯以外の方は限度額適用認定証(※ただし一般区分・現役並みⅢは認定証がありません)
・70歳未満、70歳以上の方ともに住民税非課税の方は限度額適用・標準限度額認定証
※70歳以上の一般区分の方は認定証の申請は不要であり、医療機関の窓口で自動的に自己負担限度額までの請求になります。また、3割負担の方で現役並みⅢの方は、一般区分同様認定証はなく、窓口で自動的に自己負担限度額までの請求になります。ただし、保険証のみでは現役並みⅢか否かが判断できません。その為3割負担の方は、健康保険の窓口にて認定証の申請についてご確認ください。
注意)国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は認定証の発行がされない場合があります。
『認定証』の申請をせずにいったん窓口で支払いをした場合も、後日保険者に申請をして払い戻しを受けることができます。ただし、高額療養費を申請して支給されるまでには、少なくとも3ヶ月程度かかります。1ヶ月に1つの医療機関での支払いが高額になる可能性がある場合は、『認定証』をあらかじめ申請しておきましょう。
なお、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)の手続きをされている場合、マイナンバーカードを利用できる医療機関窓口では、限度額適用認定証がなくても、限度額を超える支払いは免除されます。
◎注意点
○保険者によっては、高額療養費制度に該当することの通知がない場合もある
〇医療機関にかかった翌月以降に申請する
○支払い直後に申請をしていなくても、2年前までさかのぼって申請することができる
○払い戻しには、治療を受けた月から、通常3か月程度の期間がかかる
○加入している保険の種類や地域によっては、払い戻しまでの当座の支払いを支援する貸付制度や受領委任払い制度を利用することができる
その他、『世帯合算』(世帯で複数の方が同月に医療機関で受診した場合や、一人で複数の医療機関で受診する場合など、自己負担限度額を世帯で合算できる。その合計額が自己負担限度額を超えた場合、後日加入する保険者に申請することで高額療養費が支給される)、『高額医療・高額介護合算療養費制度』(世帯内の同一の医療保険加入者について、1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計して、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度。同一世帯で医療と介護でかかった費用の負担が軽くなる)などがあります。
ただし、これらも注意点があり、複雑なところもあるので、まずかかっている病院のソーシャルワーカーにご相談ください。
高額療養費制度に関して、詳しくはご自身が加入している保険者(保険証、資格確認証に記載されています)までお問い合わせください。
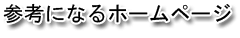 国立がん研究センター『がん情報サービス』:相談先を探す https://ganjoho.jp/public/index.html [相談先・病院をさがす]では、成人や小児の相談先・病院一覧(がん診療連携拠点病院、小児がん拠点病院)を病名や地域、病院の種類などから探すことができます。 |
ご意見・ご感想
よりよい情報提供を行うために、ご意見やご感想をお寄せください。
いただいた評価やご意見・ご感想は、今後、このコンテンツ(情報のなかみ)に役立たせていただきます。
なお、個別の回答やご相談は、仕組み上できかねますので、お困りごとやご相談がある方は、下記「がん相談支援センター」をご利用ください。
【がん相談支援センター】
お困りごとやご相談がある方は、●静岡県内の方は、
静岡がんセンター「よろず相談」
もしくは、静岡県内のお近くのがん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター」
●静岡県外の方は、
お近くのがん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター」
にご相談ください。
がん体験者の悩みQ&A
がん体験者の悩みQ&A
- 悩みと助言
- 静岡県 医療と暮らしの情報
- 発行した冊子
- 電子書籍
- がん体験者の悩みを知る
- このサイトについて