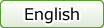悩み
食べ物が気管に入りかけたり、喉にひっかかったりして咳き込むことが辛く、呼吸困難になることもある。
助言
自分の助言集をつくる
EPUB形式でダウンロード 印刷用表示
印刷用表示
【嚥下障害とは】
嚥下障害とは、食べるとむせたり、飲み込みにくくなったりして食べることが困難になることです。嚥下障害は加齢や体力低下、治療の影響によって起こります。
うまく飲み込めずに、食べ物が気管や肺に入ってしまうと(誤嚥:ごえん)、窒息や肺炎を起こすことがあるので、大変危険です。
飲食物を飲み込むというからだの仕組みは複雑です。飲食物が咽頭に入ると、鼻、気道との通路がふさがれ、食道が開いて胃に送り込まれていきます。この複雑な協調運動のどこに原因があるかによって、対処法は異なります。
咽頭筋の収縮が不十分であれば、あごをひくと飲み込みやすくなります。一方、食べ物を後方に送り込む舌の力が弱いときには、あごを上げるとよいです。
食事の飲み込みに困られているなら、担当医に相談してください。飲み込みに関するリハビリの専門家として、言語聴覚士がいる病院もあります。原因別に、食事のときの姿勢や、飲み込むコツを教えてもらうとよいでしょう。
姿勢のほか、食物の形態も飲み込みに関係します。サラサラしたもの、あるいはドロドロしたもの、どういった飲食物が摂りやすいかは、患者さんご自身がよく把握されていると思います。
【食べやすくする工夫・対応】
飲み込みにくいものは、ひと手間かけて安全な食事を心がけましょう。
飲み込みにくいもの別に、食べやすくする工夫・対応をまとめました。
(1)サラサラした液体(水、汁もの)
とろみをつけましょう。
○市販のとろみ剤を利用する
○片栗やくずを使う
○粘りけのある食材を使う
(2)バラバラするもの(口の中で小片となってばらけるもの)
まとまる工夫をしましょう。
○あんでとじたり、とろみをつけたりする
○ゼラチンや寒天で固める
○つなぎをいれる
(3)パサパサするもの(パン、ふかしいも、ゆで卵の黄身、焼き魚)
適度な水分・油分を加えましょう。
○煮たり、蒸したりする
○あんでとじる
○マヨネーズなど油脂類を加える
(4)かたく、かみにくいもの(こんにゃく、イカ、こぼう)、はりつきやすいもの(のり、わかめ、もち)
○繊維質を断つなど、切り方を工夫する
○やわらかくする下処理をする
○他の食べやすい食材に混ぜる
○肉はひき肉を利用するなど材料を考える
○無理なものは控える
ご意見・ご感想
よりよい情報提供を行うために、ご意見やご感想をお寄せください。
いただいた評価やご意見・ご感想は、今後、このコンテンツ(情報のなかみ)に役立たせていただきます。
なお、個別の回答やご相談は、仕組み上できかねますので、お困りごとやご相談がある方は、下記「がん相談支援センター」をご利用ください。
【がん相談支援センター】
お困りごとやご相談がある方は、●静岡県内の方は、
静岡がんセンター「よろず相談」
もしくは、静岡県内のお近くのがん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター」
●静岡県外の方は、
お近くのがん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター」
にご相談ください。
がん体験者の悩みQ&A
がん体験者の悩みQ&A
- 悩みと助言
- 静岡県 医療と暮らしの情報
- 発行した冊子
- 電子書籍
- がん体験者の悩みを知る
- このサイトについて