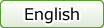悩み
病気のことをあれこれと主治医に聞くと、「患者はあなただけではない、そんなに気にする患者は嫌い」と言われ、それから質問できなくなった。
助言
自分の助言集をつくる
EPUB形式でダウンロード 印刷用表示
印刷用表示
【相談窓口に相談する】
ご自分の病気の状態や治療の副作用・合併症などをよく理解することが安心につながることも多いと思います。
あなたの身体の状態をもっとも知っている担当医に確認することが一番ですが、言いにくいときや思いが伝わりにくいときには、病院の相談窓口に相談してみてください。また、担当医と話すとき、家族に同席してもらうとよいでしょう。
【医療者とうまくコミュニケーションをとっていくために】
医療者とうまくコミュニケーションをとっていくためには、あなた自身が積極的に働きかけることや、短い時間であっても、医療者と向き合う時間を有効に使っていく工夫をしていくことが大切です。
最近では、がん治療も通院で行う治療が増え、また入院が必要な場合でも、以前に比べて入院期間が短くなっています。特に、外来診療では一人当たりの診療時間が短いと感じることが多いかもしれません。
そこで、あなた自身ができることをまず始めてみましょう。
1.『不安や不信』につながっている原因をご自分の中で整理してみましょう。
まず、あなたが今不安に感じていること、疑問に思っていることをノートなどに書き出します。最初は、長い文章で自由に書いてみて構いませんが、書き終わったら読み直し、最終的にかじょう書きにしてみます。
たとえば「○○の検査結果が知りたい」、「○○という症状がどうして起こっているのか知りたい」、「○○をどう対処したらよいか知りたい」などです。ただ「いろいろ聞きたいことがある」、「忙しそうで話しかけられない」というのではなく、具体的に整理することが大切です。
2. 外来の場合は、特に予習・復習をしてみましょう
短い外来時間を有効に使うためにも、予習・復習をしてみましょう。
予習は、次の外来で実施予定の検査、あるいは結果の出ている検査、今ある症状や困っていること、担当医や看護師に聞きたいことを書き出し、整理してみることです。これは、できるだけ1行以内の箇条書きにして、間に空欄を入れておきます。この空欄は診察時や復習のときに使います。
復習は、診察室での診療のなかで、大切なことを自分なりに書き出して、まとめてみることです。その場では、すぐ聞けなかった疑問などがあったら、次の外来時に確認できるように、予習のところに、箇条書きで加えておきましょう。
3. 疑問、不明なことをそのままにしておかない
疑問や不明なことをそのままにしておいてはいけません。そのままにしておくと、少しずつコミュニケーションのずれが積み重なり、不信感につながります。
医師は説明したつもり、患者さんはわかったつもりでは、信頼関係を築くのは難しいでしょう。
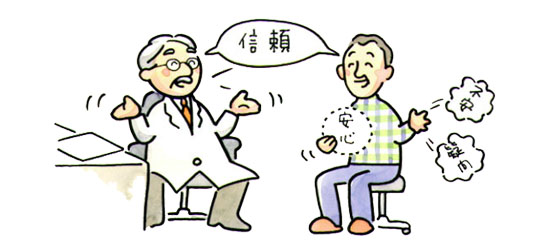
ご意見・ご感想
よりよい情報提供を行うために、ご意見やご感想をお寄せください。
いただいた評価やご意見・ご感想は、今後、このコンテンツ(情報のなかみ)に役立たせていただきます。
なお、個別の回答やご相談は、仕組み上できかねますので、お困りごとやご相談がある方は、下記「がん相談支援センター」をご利用ください。
【がん相談支援センター】
お困りごとやご相談がある方は、●静岡県内の方は、
静岡がんセンター「よろず相談」
もしくは、静岡県内のお近くのがん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター」
●静岡県外の方は、
お近くのがん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター」
にご相談ください。
がん体験者の悩みQ&A
がん体験者の悩みQ&A
- 悩みと助言
- 静岡県 医療と暮らしの情報
- 発行した冊子
- 電子書籍
- がん体験者の悩みを知る
- このサイトについて