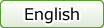悩み
日常生活をどのようにすればいいのかなど、先生がきちんと説明してくれないのでとても心配した。
助言
自分の助言集をつくる
EPUB形式でダウンロード 印刷用表示
印刷用表示
【説明がなければ確認する】
医師から説明がないようでしたら、ご自分から積極的に確認してみましょう。わからないことをわからないままにしておくことは自分自身にとってマイナスになります。ただ、なかなかタイミング良く質問できないこともあると思います。自分の知りたい情報を得るためには、要領よく具体的に質問できるように準備しておきましょう。
まず「日常生活」とありますが、これはとても幅が広いと思います。たとえば、家事をどこまでやってよいのか、○○のスポーツをやっていたが、退院後はできるのか、外出はしてよいのか、食事に制限はないのか等、自分の入院前の生活時間や行動の特徴を思い出しながら、気になっている点を箇条書きなどで書き出してみましょう。
【自分で自分のペースを見つけていく】
日常生活の制限は特にないという場合もあります。よく聞くのが、「無理をしない程度に」という患者さんにとっては、あいまいな表現のものです。ただ、生活や行動に制限がない場合、自分のからだのコントロールは自分で覚え、身につけていくしかありませんから、少しあいまいな表現になってしまうのかもしれません。体力、筋力、からだのなかの臓器の力(心肺機能など)などは一人ひとり異なります。回復の時間も人によって異なります。
特に制限がない場合は、まず『八分目』を意識しましょう。家事をするにしても、最初は八分目、仕事も最初は八分目、お子さんの世話も八分目といった具合です。この八分目は、“もうちょっとがんばれそうだけど”というところで、やめておくことです。あるいは休息をとることです。からだにもこころにも、常に意識して余裕(ゆとり)をもたせておきます。そのうちに、同じ作業(行動)をしているのに、疲れにくくなったとか、早くできるようになったとか気づくことがあるでしょう。このようにして、ゆとりを持ちながら自分のペースで生活を再構築していきましょう。
ご意見・ご感想
よりよい情報提供を行うために、ご意見やご感想をお寄せください。
いただいた評価やご意見・ご感想は、今後、このコンテンツ(情報のなかみ)に役立たせていただきます。
なお、個別の回答やご相談は、仕組み上できかねますので、お困りごとやご相談がある方は、下記「がん相談支援センター」をご利用ください。
【がん相談支援センター】
お困りごとやご相談がある方は、●静岡県内の方は、
静岡がんセンター「よろず相談」
もしくは、静岡県内のお近くのがん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター」
●静岡県外の方は、
お近くのがん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター」
にご相談ください。
がん体験者の悩みQ&A
がん体験者の悩みQ&A
- 悩みと助言
- 静岡県 医療と暮らしの情報
- 発行した冊子
- 電子書籍
- がん体験者の悩みを知る
- このサイトについて