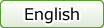悩み
告知に関する話し方、タイミング等の配慮が全くなく、あまりにも事務的すぎて我が耳を疑った。
助言
自分の助言集をつくる
EPUB形式でダウンロード 印刷用表示
印刷用表示
【本人への告知】
現在では、がんの告知を患者さん本人にする病院が増えてきました。これにはいろいろな理由があります。
1つには、本人への告知を希望する人が日本でも増えているということです。自分の病気なのだから自分自身の問題として受けとめたいということだと思います。
最善の治療を行っていくためには患者さんと医療者の間で情報を共有し、コミュニケーションをとり、協力して治療にあたることが大切です。そこで、自分の病気の状態、治療の具体的内容、なぜその治療が必要なのかを理解することが協力して治療にあたる第一歩と言えるでしょう。
【告知のショック】
一方で、がんの告知後は強いショックを受け、頭が真っ白になり、医師が何を言ったか全く覚えていないとか、やはり聞きたくなかったとか、こころは大きく動揺します。
けれども、こういったショックや動揺は、時間をかけて少しずつやわらいでいきます。
また、病気の状況や治療について知っていくことで、未知のものへの不安は徐々に少なくなっていきます。
【説明を受ける患者さんとご家族の心構え】
診断の結果を聞くときには、患者さんもご家族もとても緊張しています。特にその前にがんの疑いがあるという話を聞いていると、さらにその不安と緊張は大きいと思います。
ここでは説明を受ける患者さんの側がどうしたらいいかについて、いくつかお話ししたいと思います。
1. 医師から病気や治療の説明を受けるときは、家族や親しい人に同席してもらいましょう
これは、心強さという面もありますが、医師の前ではほとんどの方が緊張します。特に診断結果や治療について聞くときは、内容によっては激しいショックや動揺が起こります。このようなときに、医師の説明のすべてを理解するというのは難しいものです。また、説明でよくわからないことがあっても、そのまま聞き流したり、説明が音としては耳に入ってくるのに後で思い返すと全く覚えていないということもあります。
2. メモをとるようにしましょう
医師の説明を聞くときには、メモを用意し、重要だと思ったことなどをメモしましょう。説明を聞きながらメモをとるのは自信がないということであれば、医師に申し出て、説明を録音してもよいでしょう。ただし内緒で録音するというのは、礼儀に反し、その医師との関係を損ねる原因にもなります。録音する場合は、必ず医師に断ってからにしましょう。
3. わからない言葉があれば、途中でも確認しましょう
医師はなるべく患者さんにわかりやすい言葉を用いるつもりではいるのですが、無意識に専門用語を使用していることがあります。わからない言葉や内容があったら、医師の説明の途中でも、どういう意味か聞きましょう。
3. 気持ちが落ち着いてから、同席した方と、わからなかったことを確認しあいましょう
たとえ、こころの準備をしていても、その場では緊張と動揺で質問する余裕はないかもしれません。
その場合は、自宅に戻ってもう一度同席した方と話をしながら、わからなかったことを確認し、次回の外来の時などに確認しましょう。ショックや動揺が強い場合は、少し気持ちが落ち着いてからでもかまいません。

ご意見・ご感想
よりよい情報提供を行うために、ご意見やご感想をお寄せください。
いただいた評価やご意見・ご感想は、今後、このコンテンツ(情報のなかみ)に役立たせていただきます。
なお、個別の回答やご相談は、仕組み上できかねますので、お困りごとやご相談がある方は、下記「がん相談支援センター」をご利用ください。
【がん相談支援センター】
お困りごとやご相談がある方は、●静岡県内の方は、
静岡がんセンター「よろず相談」
もしくは、静岡県内のお近くのがん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター」
●静岡県外の方は、
お近くのがん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター」
にご相談ください。
がん体験者の悩みQ&A
がん体験者の悩みQ&A
- 悩みと助言
- 静岡県 医療と暮らしの情報
- 発行した冊子
- 電子書籍
- がん体験者の悩みを知る
- このサイトについて