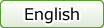悩み
毎週の抗がん剤治療は外来で行われるので体に負担がかかる。
助言
自分の助言集をつくる
EPUB形式でダウンロード 印刷用表示
印刷用表示
【治療に参加する気持ちを持ち、新しい生活リズムを取り入れていきましょう】
【通院で行われる抗がん薬治療】
最近では、抗がん薬治療(細胞障害性抗がん薬、ホルモン療法薬、分子標的薬など)を通院で実施する医療機関が増えてきました。
これは、抗がん薬の副作用を軽減するための薬(吐き気止めなど)や、その他の対処方法も進歩し、これまで入院して行っていた治療も通院で行われるようになってきたからです。
患者さんが安心して抗がん薬治療を受けられるように、病院によっては通院治療を行うための部屋(通院治療センターなどの名称で呼ばれています)を開設し、専任スタッフを配置したり、リクライニングチェアやベッドを備えたりしています。医師だけではなく、看護師、薬剤師など多職種の医療スタッフが、患者さんが安心して治療が受けられるような環境を提供しています。
通院で行われる抗がん薬治療は、病院を一歩出ると医療者がそばにいないことになりますから、不安がつのることもあるでしょう。
その一方、精神的な状態に左右されやすい吐き気や食欲不振も、入院して治療を受ける場合よりもかえって少ない、と話される患者さんもいます。また、知らない他人と同室で24時間過ごす日々ではなく、治療が終わると、自分の慣れ親しんだ自宅に戻り、リラックスできると言われた患者さんもいらっしゃいます。ご家族が、同じ空間にいることも安心や心の落ち着きにつながるかもしれません。
【あなた自身も治療に参加する気持ちで】
抗がん薬治療を受けているときは、看護師や薬剤師などから注意する点など説明があると思いますが、点滴の針を刺している部分が痛くなったり、気分が悪くなったりしたときには、遠慮なく、すぐに看護師に声をかけましょう。
同じ治療を何コースか繰り返す場合、1~2回目は、特に注意深く、体調の変化、副作用の出方や変化などをメモしておきましょう。メモを取っておけば、後で担当医に確認できますし、以後の治療を受ける際に自分の体調の変化を予想しやすくなります。
また、自分で試してみた副作用への対処法(食べやすい食事、吐き気があるときに楽な姿勢など)の中で効果があったものは、次回の治療の際にも実行してみましょう。
自分の治療に積極的に参加する気持ちをもつことで、医師の話も集中して聞くことができるようになります。不明な点、気がかりがあれば、その都度確認するようにしましょう。
【通院治療と日常生活を考えながら、生活のリズムを作りましょう】
入院中は、ある意味では、『患者としての自分』の生活がずっと続くことになります。
これに対して、通院して治療を受ける場合には、『患者としての自分』だけでなく、患者さんによっては、仕事に行ったり、学校に通ったり、家事をしたり、また、近所の方々と話したり、友人や知人と出かけたりする『社会の中で生活している自分』を感じることができると思います。
自分の居場所や役割を再確認したり、社会の中で“地面に足をしっかりとつけて立っている”という感覚をもつことは、あなたにとっての支えや生きがいにつながることもあるはずです。
ただ、『患者としての自分』と『生活者としての自分』という二つの役割を常に全力投球で行っていると、疲れたり、つらく感じたりすることもあるかもしれません。
治療前、治療中、治療後の体調の変化を見きわめながら、自分のペースで生活のリズムを作り出していくことが大切です。
だるさや疲労感というのは、まわりの人にはなかなか伝わりにくいものです。あなたの体調の変化を周囲の人に伝え、つらいときにはサポートしてもらいましょう。たとえば、ご家族に対して、「抗がん剤治療の影響で、何かしたあと、すぐ横になって休むかもしれない」、「こういうときは手伝ってほしい」と話してみてください。
(最終更新日 2024年5月15日)
ご意見・ご感想
よりよい情報提供を行うために、ご意見やご感想をお寄せください。
いただいた評価やご意見・ご感想は、今後、このコンテンツ(情報のなかみ)に役立たせていただきます。
なお、個別の回答やご相談は、仕組み上できかねますので、お困りごとやご相談がある方は、下記「がん相談支援センター」をご利用ください。
【がん相談支援センター】
お困りごとやご相談がある方は、●静岡県内の方は、
静岡がんセンター「よろず相談」
もしくは、静岡県内のお近くのがん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター」
●静岡県外の方は、
お近くのがん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター」
にご相談ください。
がん体験者の悩みQ&A
がん体験者の悩みQ&A
- 悩みと助言
- 静岡県 医療と暮らしの情報
- 発行した冊子
- 電子書籍
- がん体験者の悩みを知る
- このサイトについて