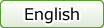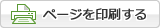修了生のメッセージ
ご覧になりたい分野を選択すると、ページが移動します。
皮膚・排泄ケア分野
2020年度修了 豊川市民病院
この研修期間を通して、自分自身と向き合うことが重要であり、組織人としてのスペシャリストの立ち居振る舞いやロジカルシンキングをした上で論理的に伝達するという目標ができました。また、専門的知識だけでなく「考える力」を養うことができました。さらに、「ケア方法に正解はなく、ゴールに辿り着くための思考過程が大切である」という言葉に、看護の悩みのあった私の心は救われました。加えて、創傷やストーマ管理、排泄管理における臨床推論力・病態判断力などの新たな知見を得たことで、看護に対しての自信が持てるようになりました。
現在は、褥瘡外来やフットケア外来に携わり、特定行為の経験を積むことができています。また、当院は三次救急医療体制の強化を重点目標に挙げられており、医療関連機器圧迫創傷の増加が懸念されます。その予防・指導へ繋げる取り組みを通して、今後は少しずつ自身の活動を広げていきたいと思っています。
緩和ケア分野
2020年度修了 茅ヶ崎市立病院
症状マネジメントは緩和ケアの要であり、症状のメカニズムを理解し、どのような方法が効果的であるのか、適した薬剤の種類や量、投与経路の妥当性を検討し評価することが専門家としての礎になることを学びました。また、特定行為研修の受講により学んだ臨床推論力や病態の理解は、より質の高い症状マネジメントの実践やニーズに応じた迅速な対応に活かせると考えています。
現在は、緩和ケアチームの活動に携わっています。院内を横断的に活動するにあたり、さまざまな人の立場や状況を理解し、俯瞰した視点で調整する役割が求められます。その際には、他者の考えを理解する力や思考を適切に言語化し論理的に伝える力、交渉する力が必要となり、研修中に学んだ言語化することの重要性について身をもって実感しています。根拠に基づいた提言ができるよう、今後も研鑽し続けていきたいと思います。
がん薬物療法看護分野
2020年度修了 国立病院機構東近江総合医療センター
専門的な知識を持つことで、安全・安楽・確実ながん薬物療法看護を提供できると思い、認定看護師教育課程を志望しました。研修中は専門的な知識だけでなく、包括的に患者をみることの重要性を学び、いかに狭い視野で患者と関わっていたかを痛感する毎日でした。こうした毎日は、自分の実践したい看護とは何かを振り返る機会となりました。そして、研修では自分の考えを言語化する技術など、認定看護師の立場で患者や多職種と関わるためのスキルを学び、自施設で求められる自分の役割を考えることに繋がりました。
現在は、外来化学療法室で勤務しながら、薬物療法の知識だけでなく特定行為研修で学んだ臨床推論やフィジカルアセスメントの知識も生かし、教育課程での学びを患者・家族に還元できるように奮闘しています。今後は、施設として安全・安楽・確実ながん薬物療法看護を提供できるよう看護の質向上を目指し、尽力していきたいと思います。
がん放射線療法看護分野
2020年度修了 富士宮市立病院
認定校では自分と異なる考え方や価値観に触れることができ、視野を広げることができました。これまでの私は独りよがりで自分のペースで業務を進めてしまいがちでした。自己を内省することで、相手の立場や意見を尊重すること、仲間に相談し頼ること、俯瞰して観るなど、スペシャリストを目指す者としての自分を見つめ直すことができました。互いに刺激し、共に学び、情報や意見交換できる仲間とのネットワークは今でも大切にしています。
現在は放射線治療室の専従看護師として勤務しています。難しい症例への理論の活用と専門的知識に基づいた看護の実践、チームへの問題提示やカンファレンスの開催など、役割を見極めながら活動を行っています。特定行為研修を通して病態判断や論理的な思考が身につき、これまでよりも病態を多角的に捉え正しく把握できるようになりました。看護の視点を基盤に治療に踏み込んだ医師や専門職との円滑なディスカッションは、有害事象への早期対応、重症化予防など治療の完遂に向けた支援に繋がっていると感じています。
乳がん看護分野
2020年度修了 和泉市立総合医療センター
特定行為を含む研修を受講し、病態生理学や乳がん治療の専門科目を学んだことで、医学的な知識が増えました。それにより、フィジカルアセスメントや臨床推論の思考が深まったと感じます。更に乳がん患者の思考過程を学んだことで、告知後の心理状態やボディイメージの受容段階を判断し、段階に応じた関わりを行えるようになりました。一つ一つ理論を基に丁寧にアセスメントし、一側面だけでなく全人的に捉えることで、セルフケア支援が変化し、根拠に基づいた看護を行えるようになりました。
またグループワークにおいて、専門性の違いや価値観の違いを理解した上で、課題達成のために意見交換をしたことが、自身の積極性や協調性の考え方に変化をもたらしました。組織の中で求められている役割としての意見を積極的に伝え、他職種がそれぞれ専門性を発揮できるように、橋渡し役として必要な協調性を研修期間を通して培うことができたと感じています。