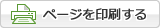主な診断方法・治療法・手術件数
主な診断方法
画像診断(MRI、CTスキャン、骨シンチ)
MRI検査は、腫瘍がある範囲、大きさや深さを調べるための画像検査です。腫瘍の性質も推測できる場合もあります。
CTスキャンは、内臓への転移の有無を知るために行います。造影剤を使用することにより腫瘍に栄養を送り込んでいる血管の特定も可能です。
骨シンチは、一回の検査で、全身の骨の腫瘍や細菌感染による異常を調べることができる検査です。骨転移を起こしている箇所を特定することができます。
下針生検
CTスキャンや超音波検査(エコー)を撮影しながら病巣部に特殊な針を刺し、病理検査に提出するための腫瘍組織を採取します。
切開生検
手術室で腫瘍の近くを切開し、肉眼で腫瘍を確認した後に腫瘍組織を採取して病理検査に提出するための組織を採取します。
病理検査
生検で得られた組織を顕微鏡で見て、腫瘍の分類や良性悪性の判断を行います。
遺伝子解析
ユーイング肉腫や滑膜肉腫、横紋筋肉腫などは腫瘍細胞が特有の遺伝子異常を持っていることが多いので、腫瘍組織の遺伝子異常を調べることで、診断をより正確にするための検査です。
主な治療法
骨肉腫、ユーイング肉腫
生検による診断確定後、まず約3カ月に及ぶ術前化学療法を、次いで広範切除及び人工関節あるいは処理骨による再建を行います。手術後3から4週で手術後の化学療法を開始し、数ヵ月にわたる化学療法後に退院となります。
軟骨肉腫
切除可能な場合は広範切除を行います。化学療法は通常行いません。
高悪性度軟部肉腫
切除可能な場合
年齢が70歳未満で内臓の機能に問題がなければ、約3カ月間の手術前化学療法を行い、その後広範切除を行います。手術後3から4週で傷口が良くなったら約2カ月間の手術後の化学療法を行います。
切除が不可能な場合
腫瘍を小さくするために放射線治療を行います。状態により化学療法を併用したり、陽子線治療を追加することもあります。
内臓に転移がある場合
年齢や全身状態に応じた化学療法を行います。
骨巨細胞腫
手術が可能な場合は掻爬骨移植という手術を行います。これは病巣部を いろいろな器具を用いて掻きだし除去(掻爬)した後に、人工骨や自分の骨(自家骨)を骨盤や脛の外側から採取して移植(骨移植)する方法です。再発している場合や手術で切除が困難な場合には抗RANKL抗体という薬物を投与します。
軟骨芽細胞腫、動脈瘤様骨嚢腫
手術が可能な場合は掻爬骨移植という手術を行います。
類骨骨腫
CTやMRIで病巣部をピンポイントで同定し、そこだけをくりぬくように切除します。切除後に周辺を加熱処理して再発を防止することもあります。
高分化型脂肪肉腫
腫瘍の周囲の部分で腫瘍を切除する手術(腫瘍辺縁切除術)を行います。
転移性骨腫瘍
9割以上の症例は放射線治療で治療しますが、骨折を起こしている場合や、放射線治療が効かない場合は手術を行うこともあります。骨折を起こしそうな場合は短期入院をしてリハビリテーションを行うこともあります。可能なら骨の転移の進行を抑制するためにビスホスホネートあるいは抗RANKL抗体という薬物を投与します。
その他
その他の良性骨軟部腫瘍(神経鞘腫、血管腫、内軟骨腫、外骨腫、骨嚢腫など)症状や発生部位により手術をする場合と経過観察のみを行う場合があります
用語解説
- 広範切除
悪性細胞の取り残しがないように、腫瘍を周囲の正常な組織で包み込み一塊として切除する手術です。
- 術前化学療法
手術前に約3カ月の時間をかけて行う抗がん剤治療のことです。腫瘍を縮小させて再発率を下げ、より良好な術後機能を得ることが目標です。腫瘍の種類や年齢により使用する抗がん剤や投与する回数は異なります。
- 術後化学療法
手術後に残存しているかもしれない悪性の細胞を死滅させ、再発率を下げるために行う抗がん剤治療です。腫瘍の種類や年齢により使用する抗がん剤の種類や投与する回数は異なります。
- 処理骨
腫瘍細胞は50°以上の加熱や急速凍結により死滅することが知られています。この原理を応用し、腫瘍が残ったままの骨に加熱や液体窒素による凍結処理を行い腫瘍細胞を死滅させてから再度体内に戻す再建方法です。
手術件数 2024年1月~12月
| 手術名 | 件数 |
| 良性軟部腫瘍切除術 | 81 |
| 悪性軟部腫瘍広範切除術 | 60 |
| 良性骨腫瘍切除または掻爬 | 11 |
| 悪性骨腫瘍広範切除術 | 20 |
| 転移性骨腫瘍手術 | 13 |
| 切開生検 | 98 |
| その他 | 41 |
| 合計 | 324 |