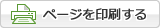レジデント向け情報
研修の特徴
静岡がんセンター感染症フェローシップは、2005年4月にコースを開始しました。感染症内科は、がん治療における合併症対策の要であり、がん患者さんが安心して治療に専念できるよう支援することが、私たちの役割です。近年では、がん領域に限らず、医療全体において診療の質と安全性を高めるうえで、感染症専門医の果たす役割がますます重要になっています。本プログラムでは、がんに限らず、複雑な病態を有する入院患者さんの感染症マネジメントについても実践的に学ぶことができます。多様な臨床ケースを通じて、重症例や多疾患併存症例における感染症診療の知識と技術を深めることができる点も、本フェローシップの大きな特長の一つです。
当院のプログラムでは、ベッドサイドおよび外来でのコンサルテーションを中心に、臨床現場での実践的な研修を行います。さらに、カンファレンスやジャーナルクラブを通じて感染症に関する体系的な知識を深めるとともに、臨床現場や感染対策上の課題にも積極的に取り組みます。また、院内の感染対策活動にも積極的に関与し、将来的に感染対策チーム(ICT)や抗菌薬適正使用支援チーム(AST)のリーダーとして活躍できる力を育成することを目指しています。
地域への貢献
静岡がんセンター感染症内科では、院内にとどまらず、地域全体の感染症診療・対策の向上にも積極的に取り組んでいます。
当科では、経時的に近隣医療機関の研修医を受け入れ、実践的な感染症診療の研修機会を提供しています。また、定期的に勉強会を開催し、院内外の医療従事者を対象とした知識共有を行っています。さらに、医師会や地域医療機関と連携し、地域全体の勉強会の講師としても活動しています。加えて、近隣の病院・診療所・高齢者施設等に対して、感染対策の支援や臨床に関するアドバイスも積極的に行っており、感染症に関する地域の相談窓口としての役割も担っています。
感染症を学び、地域の感染症診療を向上させたいと考えている方を、私たちは全力で支援いたします。関心のある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
研修内容と実績
当院には、感染症専門医資格を有する指導医が在籍しており、感染症専門医制度に基づいた体系的な研修を提供できる体制が整っています。研修は2年コースと3年コースから選択できます。1年以下の短期間をご希望される方はご相談ください。
1. 研修で経験できる主な内容
入院患者の感染症
がん患者における発熱性好中球減少症、真菌感染症等への対応
手術関連感染症(術後感染症、予防、人工物関連感染症など)
造血幹細胞移植後の感染症(治療、移植後ワクチン対応)
多剤耐性菌への対応(治療および感染対策)
抗菌薬の適正使用(選択・投与設計・モニタリング)
感染対策チーム(ICT)、抗菌薬適正使用チーム(AST)への参画
ワクチン外来や寄生虫感染症などの専門診療の経験
地域感染症ネットワークの構築・院外カンファレンスへの参加
2. 2023年度診療数
|
感染症内科総患者数 |
1704 |
|
コンサルテーション数 |
760 |
|
ワクチン接種 |
113 |
|
感染対策実施件数 |
1048 |
|
AST介入回数 |
1674 |
3. 1日の流れ
週間予定の一例
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|
担当患者回診等 |
||||
|
全体共有・症例相談 9:45 ~ 10:00 |
||||
|
検査室ミーティング 10:00 ~ 10:15 |
||||
|
|
||||
|
|
抄読会/統計勉強会 など 12:30~13:30 |
|
||
|
|
カンファレンス 13:00 ~ 14:00 |
|||
|
カンファレンス 13:30 ~ 14:30 |
カンファレンス 13:30 ~ 14:30 |
|||
|
ICTラウンド 14:30~ |
||||
|
|
|
|||
|
AST 15:00 |
||||
|
|
||||
|
|
感染対策室ミーティンク/ICT 16:00~ |
|
||
|
|
||||
|
|
ICT/ASTミーティング 17:00 ~ (第2火曜) |
院内勉強会 18:00~ (月2回) |
院外勉強会 18:00 ~ (第4木曜) |
|
研修コースと研修内容
2年コースと3年コースがあります。
当院は感染症専門医資格を有する暫定指導医が所属します。よって当院で3年間の修練を積めば、同学会の専門医試験の受験要件を満たします。詳しくはこちらを御覧ください。
レジデントの声
倉員 侑己(くらかずゆうき) 感染症専門修練医
感染症診療について
当院はがんセンターという施設柄、がん患者の感染症に強くなります。また、もちろんがん患者さんも市中感染症には罹患しますし、がん自体による解剖学的異常や治療に伴う留置デバイス、化学・放射線療法やステロイドなどが絡み合う病態を紐解く上で、“感染症診療の原則”の重要性を日々強く感じます。施設によらずフェローシップ期間中に経験できる症例には限りがあるので、基本的な考え方がしっかりと身につけば今後遭遇する疾患に対しても応用することができると思います。当科ではフェローとスタッフが症例ごとにペアを組んで診療に当たっており、毎日カンファレンスを行い全員でディスカッションしながら症例を一例一例積み重ねていくことができます。血液培養ラウンド
当院では年間約600例の血液培養陽性症例がありますが、全症例のグラム染色を細菌検査技師と医師で確認し、抗菌薬治療の提案も含めて陽性報告を行っています。鏡検を繰り返していくうちに菌の見分けがつくようになり、スキルアップを実感することができます。触れる機会が多い分、微生物に強くなることができると思います。日報での学び
当院の感染症フェローシップが開始されてから20年が経ちますが、学んだことを“日報”として共有する当時からの文化があります。アウトプットの場にもなりますし、他の先生方の学びも共有されるので、自分が気になったものはそこから文献を見ていくことで学びの量も多く効率も良いと思います。各種勉強会
当院では科内の抄読会や、院内や県内他院の医師・研修医・コメディカル向けの“コアカリキュラム”と題した勉強会を通年で行っています。コアカリキュラムは月1-2回実施しており、一通りの感染症をある程度網羅的に学べるように予定を組んでおり、毎年新しいテーマも取り入れるようにしております。例を挙げると2024年度は「感受性検査をどう臨床に生かすか」、2025年度は「感染症治療がうまくいかないときの考え方」など、あまり聞く機会がないテーマを取り入れており、作る側の勉強になるのは間違いないです。職場環境の良さ
休みが取りやすい、町が住みやすい、これに尽きます。
富士山は登るより見る派ですが、毎日富士山を眺めながらの出勤も風情があります。
がん患者の感染症というのは市中感染症からすれば一見特殊にも思われるかもしれませんが、がんセンターではなくてもがん患者の感染症を診る機会は多いはずで、強みを1つ持てるようになるのは当院の感染症専門修練医(感染症フェローシップ)プログラムの強みの1つだと思います。
募集情報
当院のフェローは卒後5年目以降の内科についてある程度の知識と経験を持つ医師を中心に募集を行なっています。また短期間(1ヶ月~1年)でもがん患者の感染症について学びたい方はご相談下さい。