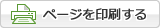主な診断方法・治療法・手術件数
主な診断方法
内視鏡検査
胃がんが疑われた場合にまず行われる検査です。のどに麻酔をした上で内視鏡を口(または鼻)から挿入し、食道から胃、十二指腸にかけてくまなく観察し、病変の有無、病変が存在する場合はその部位、大きさ、深さ(壁深達度)などを診断します。がんが疑われる部位は、組織の一部を生検(直接採取すること)し、病理検査に提出します。なお、内視鏡検査では、消化管の蠕動を止めるために薬剤が使用されますが、緑内障や前立腺肥大の患者さんには使えないので、検査前の問診時に申し出てください。
上部消化管造影検査(バリウム検査)
胃がんの集団検診でも用いられている検査ですが、胃がんと診断された場合にあらためて行う場合もあります。胃を内側から見る内視鏡検査とは異なり、胃全体の形がわかるので、がんができている場所を特定することができます。また、スキルス胃がんのように粘膜よりも深い所に広がっていくタイプでは、病変の広がりがより把握しやすくなります。とくにがんが食道や十二指腸に及んでいる場合は、広がっている範囲を診断するのに役立ちます。
腹部CT検査
胃がんの拡がりや、転移の診断に不可欠な画像検査です。最近は機器の進歩により10秒程度で腹部から骨盤部まで一気に撮影できるようになりました。胃がんそのものの深さ(壁深達度)や、周囲の臓器(膵臓、肝臓、大腸など)への浸潤の有無が判定できます。また、リンパ節や肝臓、副腎などへの転移の診断も可能です。この検査ではまず単純撮影をし、次に造影剤を注射して造影撮影を行いますが、まれにアレルギー反応を起こすことがあります。以前に造影剤で具合が悪くなった経験がある人は検査前の問診時に申し出て下さい。
腹部超音波検査
他の検査と比べて体への負担が軽い画像検査です。進行胃がんでは腫瘍そのものが見えることもありますし、大きなリンパ節転移の診断も可能で、肝転移は腹部CT検査より診断しやすい場合もあります。胃がん以外の病気の発見にも有効で、特に胆囊結石は容易に診断できます。
腹部MRI検査
腹部CT検査などで転移が疑われるものの確定できない時や、肝臓にできた腫瘍が良性か悪性か判断がつかない場合には、腹部MRI検査が有用です。最近では、造影剤を使った「造影MRI検査」によって、これまで診断できなかった小さな肝転移まで診断できるようになりました。
PET検査
ブドウ糖の一部に放射性元素を標識したFDGを用いて、腫瘍と正常組織でのブドウ糖の取り込みの差を利用してPETという装置で見る検査です。胃がんでは、がんがあっても陰性となってしまうことが多く、術前検査としてはガイドラインで推奨されていません。しかし、手術後に腫瘍マーカーが上昇しているのにCT検査などでは転移病巣が発見できない場合には全身を一度に検索できるため有用な検査です。
超音波内視鏡検査
欧米では胃がんに対して一般的に行われている検査ですが、わが国では一部の施設でしか行われていません。胃がんがどこまで深く広がっているか(=深達度)の診断ができます。早期胃がんでは内視鏡治療が可能かどうか、進行胃がんでは他臓器に浸潤しているかどうかの判断や、胃や食道に接するリンパ節の転移診断にも使われます。また、胃の粘膜下から発生する消化管間質腫瘍(GIST)の診断にも超音波内視鏡検査が利用されています。
大腸内視鏡検査
胃がんの術前に必ず行わなければならない検査ではありませんが、進行がんで大腸に浸潤が疑われる場合に行われます。一方、胃がんの手術前に大腸内視鏡検査を行うと、約5%に大腸がんが発見されることから、大腸の検査を受けたことがない人は胃がんの手術前に受けることをお勧めします。
審査腹腔鏡(診断的腹腔鏡検査)
超音波検査やCT検査などで腹膜への腹膜転移が強く疑われる場合、あるいは大きな浸潤型胃がんで腹膜転移の可能性が高い場合に行われます。通常、全身麻酔下でおなかに3カ所の穴をあけ、カメラ(腹腔鏡)を挿入しておなかの中を観察します。およそ4、5日程度の入院が必要な検査です。目に見える明らかな転移が疑われる場合には、組織の一部を切り取って調べます(生検)。腹水や腹腔洗浄液の細胞診検査(目に見えない浮遊したがん細胞の有無を調べる)も同時に行われます。また、隣接する臓器に広がっているかどうかの診断も可能です。
主な治療法
胃がん
胃がんの治療に関しては、胃癌治療ガイドライン(日本胃癌学会編)によるステージ分類別に日常診療における標準的治療と、臨床研究として行われる治療を区分して提示しています。また内視鏡科、消化器内科と合同カンファレンスを行い、一人一人の患者さんに対して適切な治療を提供できるように心がけています。
早期胃がんに対する治療方針
早期胃がんのうち一部のがんに対しては上記のガイドラインに従い内視鏡的治療が施行されています。内視鏡治療の結果によってはリンパ節郭清(リンパ節を広範囲にとる手術)を伴う胃切除術が追加で必要となります。
内視鏡的治療が適応とならない早期胃がんに対しては、リンパ節郭清を伴う胃切除術を施行します。当院では、腹腔鏡手術やロボット手術を積極的に導入しており、早期胃がんに対しては基本的に全例でこれらの手術を安全に行っております。
進行胃がんに対する治療法
進行胃がんに対する標準治療は従来開腹手術とされてきました。現在、本邦における臨床試験の結果などから、幽門側胃切除術や胃全摘術、噴門側胃切除術のいずれの術式においても、腹腔鏡手術やロボット手術の低侵襲手術も標準治療として位置づけられております。当院でも積極的に低侵襲手術を取り入れております。
近年増加している食道胃接合部がん(食道と胃の境目にできたがん)に対しては、食道への浸潤距離が短い(3cm未満)場合は開腹アプローチで行いますが、それより長い場合は開胸・開腹アプローチが必要となることもあります。
ロボット支援下胃切除術
術前のステージがI, II, IIIとIVの一部の患者さんに対し、保険診療としてロボット支援胃切除術 (幽門側胃切除術、胃全摘術、噴門側胃切除術)を施行しております。ロボット手術では、創の大きさは腹腔鏡手術と同等ですが、より精緻な手術が可能となるため、術後の合併症を軽減する可能性があることが報告されています。
集学的治療
・術後補助化学療法
治癒切除後の微小遺残腫瘍による再発予防を目的として,術後の化学療法(抗がん剤治療)が推奨されています。術後、ステージ II の患者さんで、手術でがんが全て取り切れた場合にTS-1を1年間内服します。ステージ III の患者さんにはTS-1の内服とドセタキセルの点滴の併用療法を1年間行います。
・術前化学療法
化学療法によってまず腫瘍縮小や微小転移の消滅を図り、その後手術を行う集学的治療です。
・コンバージョン手術
出血、穿孔、狭窄等の原発巣に伴う緊急症状を伴わない切除不能進行胃がんに対しては、全身化学療法が第一に推奨されております。少し前までは、コンバージョン手術の良好な成績が報告されて推奨もされていました。しかし、近年の分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤を含めた抗がん薬治療開発の目覚ましい進歩により、化学療法の成績が向上し、術後に不利益を伴う可能性がある胃切除が本当に有用なのか、明確な推奨ができなくなりました。切除不能の進行胃がんに対して一次化学療法がよく効き、切除可能となった患者さんを対象として臨床試験が進行中です。
胃粘膜下腫瘍
基本的にGIST診療ガイドラインに則って治療方針を決定しています。すなわち、腫瘍の大きさが5cm以上のもの、2cmから5cmでも増大傾向のあるもの、生検でGISTと診断されているものは切除の適応とされます。このなかで、腫瘍径が8cmを超えるもの対しては開腹手術を、8cm以下のものに対しては腹腔鏡手術を行っています。基本的にGISTであってもリンパ節転移は極めてまれなので、極力胃を残した部分切除術が選択されます。また、腫瘍径が10cmを超えるものや他臓器浸潤が明らかなものに対しては術前補助化学療法を開始し、抗がん剤の効果に応じて胃切除の時期を検討します。腹腔鏡手術の適応のなかでも、胃の内腔に向かって腫瘍が発育している腫瘍に対しては、内視鏡・腹腔鏡の合同手術(LECS)が行われます。
術後の病理検査の結果で、高リスクと診断された場合は、術後補助化学療法としてグリベックの3年間投与が推奨されます。
手術件数 2024年1月~12月
| 手術名 | 件数 |
| 胃切除例 | 194 |
| ロボット手術 | 87 |
| 腹腔鏡手術 | 52 |
| 開腹手術 | 55 |
| 腹腔鏡下胃空腸吻合術 | 6 |
| 腹腔鏡下胃局所切除術 (LECSを含む) | 10 |
| 審査腹腔鏡 | 36 |
| その他 (イレウス、胆嚢結石症など) | 17 |
| 手術名 | 件数 |
| 胃切除術 | 194 |
| 胃全摘術 | 47 |
| 噴門側胃切除術 | 14 |
| 幽門側胃切除術 | 129 |
| 幽門保存胃切除術 | 2 |
| 幽門洞切除術 | 2 |