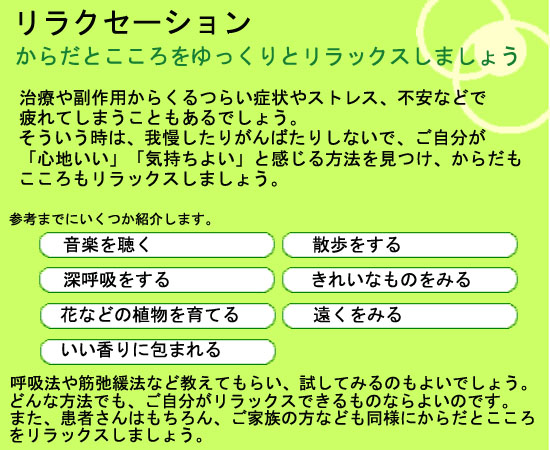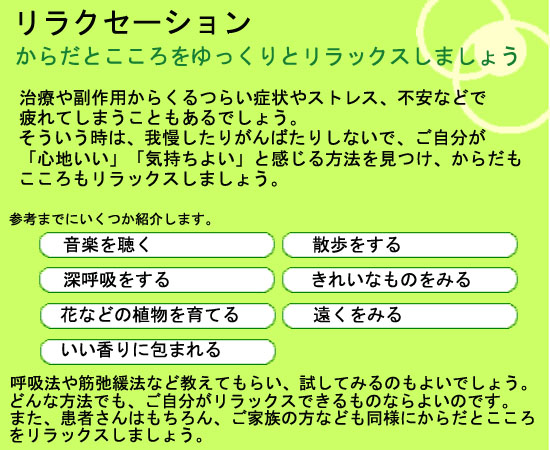悩み
乳がんのホルモン療法による更年期障害による症状(突然のほてり感や発汗など)で、不眠症に悩まされた。
助言
【ホットフラッシュ(ほてり感やのぼせ等)について】
乳がんでホルモン剤を使用していると、ホルモン環境がアンバランスになり、更年期障害のような症状が出やすくなります。これは、エストロゲンという女性ホルモンが少なくなるためです。
ほてり感やのぼせ、発汗などは『ホットフラッシュ』と呼ばれており、これは、エストロゲンが減って体温調節がうまくできなくなったり、皮膚の血流が増えたりするために起こります。
通常、こういった症状はホルモン療法の治療開始から数ヶ月くらいたつと徐々に軽くなってくるといわれています。
【日常生活上の工夫は体験者の話も聞いてみる】
通院治療のときは、外来診察の待ち時間や治療時などに顔を合わせる患者さんと話をしてみましょう。同じ体験をしたからこそ分かち合える気持ちもあります。また人に話すことで、つらさが少し楽になることもあります。もしかしたら、良いアドバイスをもらえるかもしれません。
また、患者会などに参加し情報交換してみてもよいでしょう。
【症状がひどい場合は担当医に相談してみる】
日頃の診療のなかでも、症状があるときは、担当医に報告したり相談したりすることがあると思いますが、担当医に伝えるときに、どういう症状が起こり、それが日常生活にどういう影響があるのかなど、一度整理してから伝えるようにしましょう。ただ「つらくて仕方がないので何とかなりませんか」では、相手にうまく伝わりにくいものです。
場合によっては、夜ぐっすり眠るための睡眠薬をだしてもらうことで、からだが少し楽になることもあります。
【日常生活での工夫】
◎ 急なほてり感や発汗に対応できるような服装を工夫する
急なほてり感や発汗にもすぐ対応できるように、脱ぎ着がしやすい服装(上着などで調整)を心がけてみましょう。
◎ リラクセーション
リラクセーションには、呼吸法や筋弛緩法、自律訓練法などもありますが、他にも以下のような方法があります。
○ 運動療法
難しく考える必要はありません。ストレッチ体操や散歩など、好きな運動をするだけでかまいません。適度な運動により、からだの緊張がほぐれます。からだの緊張をほぐすことで、同時にこころの緊張もゆるめていきます。
○音楽療法
リラックスできるような音楽を集めたCDなどもありますが、自分の好きな音楽を聴くことでもかまいません。
○イメージ療法
心地よいイメージを思い浮かべて、十分に心地よさを味わいます。
たとえば、緑の芝が広がった野山を歩いている・・・風がとても気持ちいい・・・鳥の声が聞こえる・・・など、簡単なイメージを浮かべることでも気持ちが落ち着いてきます。