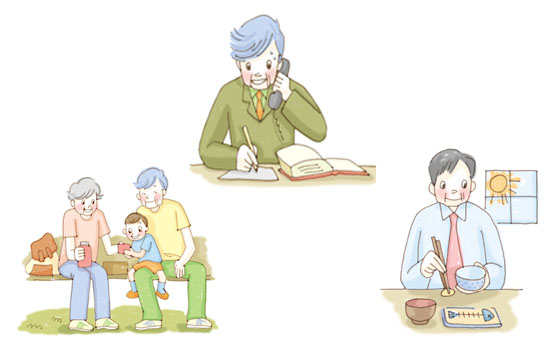悩み
思い通りにからだが動かず、病気にかかる前や治療をする前のような普通の生活ができないことの辛さがあった。
助言
【具体的な目標を作る】
がんの治療のために入院している時や、治療後の体の状態にまだなじめない退院直後は、将来の生活に対する不安や焦りを強く感じてしまいがちです。
まずは、あなたが『普通の生活』として思い描いている生活の中身を、具体的にイメージしてみましょう。
頭の中だけで整理するのが難しければ、ノートなどに書き出してみるとよいでしょう。
具体的な目標があると、達成までの道のりを一歩一歩進んでいることに気づくことができ、自信の回復につながります。
周りの人たちも、目標が具体的な方が、あなたを支えやすくなります。
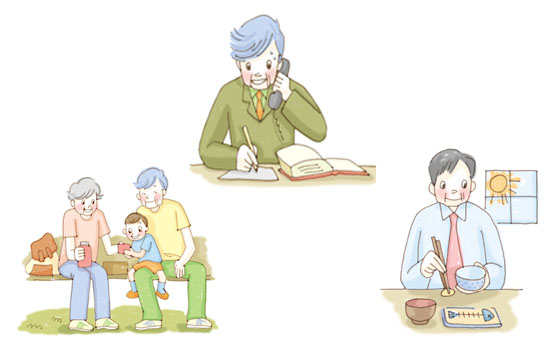
【目標と今のあなたをつなぐ『階段』を計画する】
目標が具体的にイメージできたら、次に、その目標と今の自分との間をつなぐ、あなたがのぼっていくべき『階段』を考えてみましょう。
無理をしないでいい範囲で、少しずつ、体やこころを慣らしていくことが大切です。
がんの治療が終わって、休んでいた会社に復職することを例にとってみましょう。復職するまでに、あなたに準備できることがいくつかあります。
たとえば、通勤時の移動には意外なほど体力を使うものです。まず、スーツに着替え、ラッシュアワーの電車に乗って会社の最寄駅まで行ってみて、そのまま帰宅する、という練習をしてみてはどうでしょうか。
また、最初は半日程度、それも休みながらでよいと思いますが、机について本を読んだり、文書を書いたり、パソコンで作業をしてみたりしましょう。自宅でやってみて問題ないようであれば、喫茶店や図書館に場所を移して、人が周りにいる中で作業をすることに体を慣らしていきます。
もう一つ、とても大切なことは、職場の上司や同僚に病気についてどう話すか考えて、心構えをし、準備しておくことです。家族に相手役になってもらって、話す練習してみると自信がつくと思います。
ここに挙げたもののほかにも、あなたの仕事の内容によって、必要な準備は違ってくるでしょう。
やるべき準備が見えてきたら、あなたがやりやすいと思うことから順番に並べてみて、これからのことを計画してみましょう。
復職してからも、いきなり以前のペースで仕事に打ち込むのではなく、上司や同僚と相談しながら、仕事の量や内容を調整することも大切です。
【焦らずに、自分のペースで】
目標までの『階段』を、計画通りのペースでのぼれない時にも、焦る必要はありません。
焦りがつのったり、気持ちがゆれたりした時には、ちょっと一休みしてみましょう。
そして、『階段』の先の方ではなく、これまであなたがどれだけの高さをのぼってきたか考えてみましょう。
病気の治療直後には、できるはずがない、と諦めていたことのうちのいくつかは、今はもう、できるようになっているのではないでしょうか。自信を持ってください。
そして、思い描いていた『普通の生活』とは少しちがうかもしれませんが、新しい『自分らしい生活』のイメージも、少しずつ見えてきたのではないでしょうか。
時間が経つことで、あなたの体力は少しずつ回復します。それと同時に、あなたのこころもまた、新しい状況を受け止めるための力をつけていくはずです。
時間はあなたの味方です。自分のペースで、一日一日を積み重ねていきましょう。