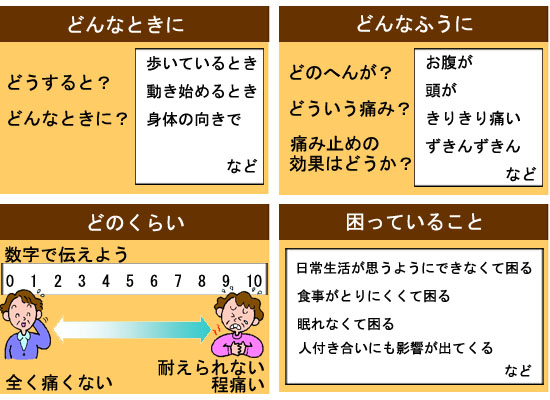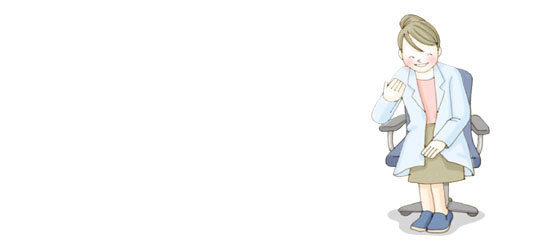悩み
食事の味がわからないことで悩んでいる。
助言
【味覚の変化】
抗がん剤、放射線治療によって、舌にある味を感じる部分や、味を感じて脳に情報を伝達する神経が影響を受け、味覚が変わることがあります。また、口の中の粘膜障害によって起こります。いろいろな原因とそれに合った対処法があります。
【唾液の働き】
唾液は、口の中を湿らせて、食物をかみ砕き、飲み込むことを容易にします。また、口の中を清潔にし、味覚を助ける働きがあります。治療の副作用で、唾液の分泌が抑制されると、口の中が乾燥したり、味覚が変化するなどの症状を伴うことがあります。
【口の中をできる限り清潔に保つ】
毎食後と就寝前に、柔らかめの歯ブラシで、歯、歯肉、舌を磨いてください。もし、磨くときに痛みがあれば、ぬるま湯を使い、より柔らかい歯ブラシで磨いてください。
強い口内炎があり、粘膜がしみる場合は、ハミガキを使わないで、水だけで歯磨きをしてもよいでしょう。
【うがいをしたり、あめをなめたりする】
口の中が汚れていると、味も変わってきます。歯磨きやうがいをすることで、口の中の汚れがとれ、味の感じ方が変わることもあります。
また、レモン水や緑茶を飲んだり、無糖の固いあめをなめたりすることも効果的です。自分に合った方法で、口の中を清潔にしましょう。
【味覚の変化や症状に合わせて、味を調整する】
「味がしない」、「味が薄すぎる」と感じる時は、味のはっきりした料理にしましょう。
味付けがはっきりしている料理とは、味付けを濃くすることもそうですが、塩分を多くとったり砂糖を多く入れたりすることばかりを言うのではありません。味をはっきりさせる工夫を参考にしましょう。
【味をはっきりとさせる工夫】
◎ だしをきかせる
塩分を増やさずに、味をはっきりさせる工夫をしましょう。
削り節を煮出した後、しばらくおいて冷ますことで、だしがよく出ます。また、シチューにバターなどの乳製品を加えたり、煮物にみりんや酒を加えたりすることで味にコクが出ます。
◎ ごま、ゆずなどの香りや、酢を利用する
酢の物にレモン、かぼす、ゆずなどを添えると酸味がよく効くようになります。
アジを素焼きにして、レモンなどをしぼって食べてみましょう。しょう油をかける時は、なるべく少量にするよう心がけます。また、片栗粉をまぶして揚げてから酢醤油につけ、南蛮風にしてみるのもよいでしょう。
◎ 食材のうまみをいかす
食材を増やすことで、具のうまみがたくさん出て味がはっきりします。
汁物を作る時は、みそやしょう油の量は普段通りで増やさずに、具をたくさんにしてみましょう。具の種類を増やしてみるのもよいでしょう。
◎ 味にアクセントをつける
味の変化が少し分かる場合には、味に変化をつけたりアクセントになるものを添えたりすることが効果的です。
からしあえ、ごまあえ、梅肉あえ、しょうが焼き、セロリやクレソンのサラダ、カレー風味など、多少の香辛料や香味野菜を用いて味に変化をつけるとよいでしょう。また、漬物などを味のアクセントにそえることも効果的です。
◎ 少し低温の料理にする
できたての温かいものを食べるよりも、少し冷めた程度の料理を食べる方がおいしく感じることがあります。
肉じゃがやシチュー、茶碗蒸しなどは、冷ましてから食べてみましょう。