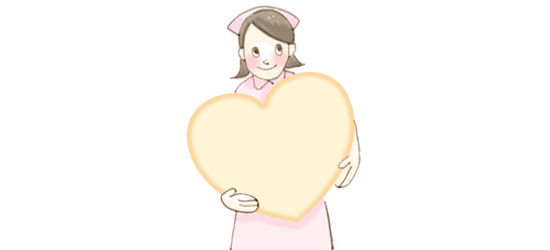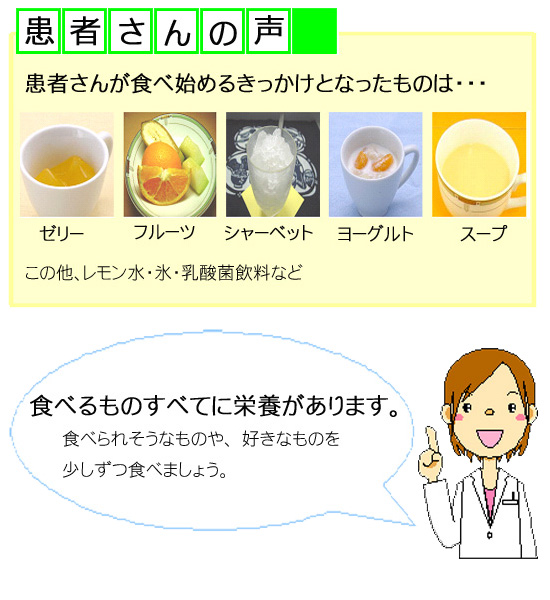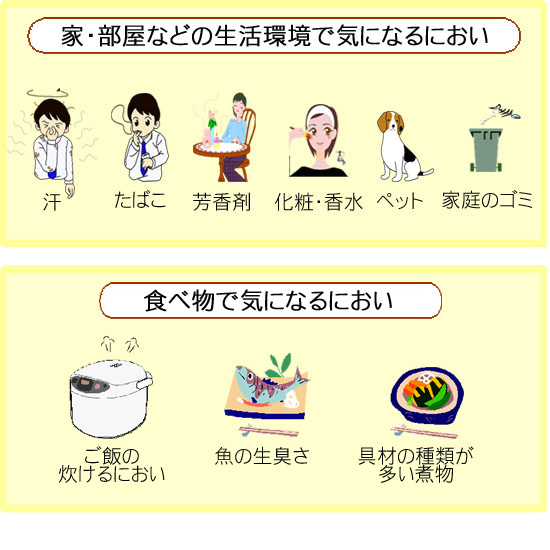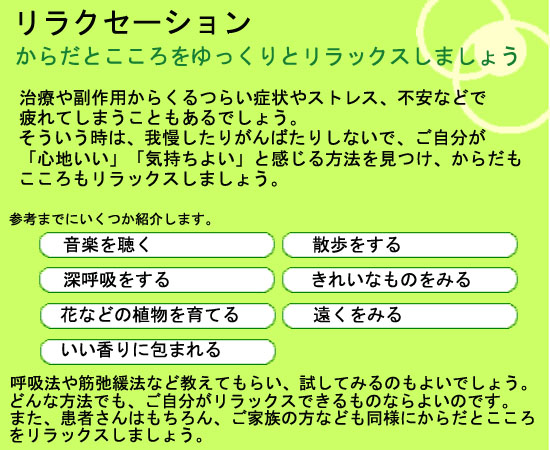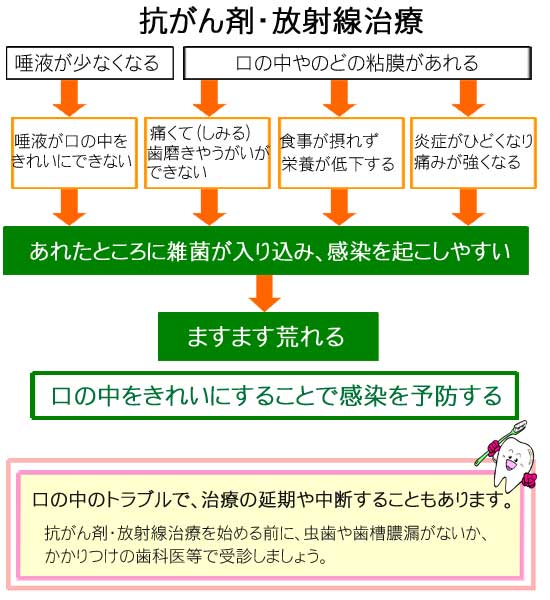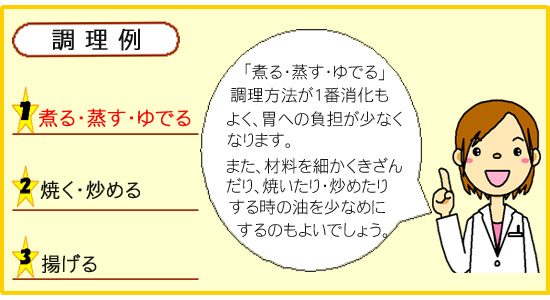悩み
抗がん剤の副作用による脱毛(髪の毛、眉毛、まつ毛、体毛)が辛く、悩んだり落ち込んだりしている。
助言
【抗がん剤による脱毛】
脱毛自体は、抗がん剤の種類により、起こるものとそうでないもの、脱毛は起こる可能性があるが軽度のものなど異なります。患者さんによっては、脱毛や吐き気があるものは強い抗がん剤、そうでないものは弱い抗がん剤と考える人がいますが、決してそうではありません。
脱毛は、治療で抗がん剤を使用してから2~3週間目から起こります。通常、抗がん剤治療は、何回か繰り返し行うので、治療を行っている間は脱毛は続きます。ただし、治療がすべて終了すれば、髪は生えてきます。
【体験者の話を聞いてみる】
たとえば、通院治療のときは、外来診察の待ち時間や治療時などに顔を合わせる患者さんと話をしてみましょう。同じ体験をしたからこそ分かち合える気持ちもあります。また人に話すことで、つらさが少し楽になることもあります。もしかしたら、良いアドバイスをもらえるかもしれません。
【自分でできることを実行してみる】
脱毛が起こりやすい抗がん剤の場合、治療や副作用の説明があったときから、できることを準備してみましょう。脱毛が始まってからも、髪や地肌をいたわるためにできることを実行してみましょう。
1. 脱毛が起こる前にできること
かなりの確率で脱毛が起こる抗がん剤を使用する場合で、かつらの購入を考えているようであれば、事前に自分の頭の写真をとっておきましょう(正面、側面、後ろ側)。こうしておくと、実際にかつらを購入するとき、あるいは購入したかつらを整えるときに、今までの自分の髪型に近いものを選ぶことができますし、購入先で相談する際にも役立ちます。
また、脱毛が始まる前に、髪を短く切っておいたほうがよいでしょう。脱毛が始まると、髪を洗ったときなどに髪がからまり、ほぐれなくなることがある(最終的には、その部分を切らざるをえなくなります)ので、からまらないようにするためです。また、ヘアカラーやパーマは、刺激になるので、やめましょう。
2. 脱毛中のケア
脱毛中は、頭皮も敏感になっているので、低刺激のシャンプーを使用し、こすらずに、優しく洗い流すようにしましょう。リンスやトリートメントは、基本的に髪に対して使用するものなので、頭皮を中心に洗い流すときは、お湯や低刺激のシャンプーだけで構いません。ドライヤーも刺激になるので、できるだけ控え、かけるときは冷風にしましょう。育毛剤も刺激になりますので、脱毛中は使わないようにしましょう。
また、脱毛は髪の毛だけではなく、眉毛・まつ毛・鼻毛などの体毛にも起こります。鼻毛がないと、鼻の中が乾燥し粘膜がいたみやすくなるため、外出時などはマスクなどを使用するとよいでしょう。眉毛は、眉ずみなどで書き、まつ毛がないと眼にごみが入りやすいため、注意しましょう。
かつらや帽子を選ぶときは、よく検討しましょう。
かつらは、借りることもできますが、手続きや申し込みから届くまでの期間などもあるので、借りることを検討しているときは、事前にホームページで確認しておきましょう。
かつらを購入するときは、1)自分にあった素材を選ぶ、2)自分にあったスタイルを選ぶ、3)自分にあったカラーを選ぶ、4)価格を検討する、5)商品の機能特性を確認する、ことが大切です。
どこで、かつらを購入したらよいかわからないときは、かかっている病院の看護師や相談室に相談してみましょう。そこでもわからないときには、お近くのがん診療連携拠点病院の相談支援センターに相談してみましょう。
帽子を選ぶ場合、生え際が気になるときは、つばの広い帽子を選びましょう。ご自宅では、スカーフやバンダナを使ってもよいかもしれません。なかには、帽子にかつらのような毛がついたタイプのものもあります。

【こころが不安定な状態が続くときは心の専門家もサポートしてくれる】
不安定なこころの状態が続くときには、一度こころの専門家に相談してみるという方法があります。
こころが不安定で、他には何も考えられなくなった、何事にも集中できない、誰とも話したくない、あるいは毎日夜眠れない、食欲がない、そういった症状が続くようなときは、担当医やこころの専門家(精神腫瘍科医、心療内科医、精神科医、臨床心理士、心理療法士、リエゾンナースなど)に相談してみてください。気持ちを落ち着けるお薬を飲んだ方がいい場合もあります。
こころの専門家というと、抵抗を感じる方もいらっしゃると思いますが、これは、がんという病気にかかったことでのこころの悲鳴だと思います。がんという病気は、それほど大きな衝撃で、激しくこころを不安定にさせたりするものだということになります。こころの問題はがんにかかった多くの方が経験することです。
がんと向き合うとき、からだのほうは、担当医がサポートしてくれますが、こころの方は周囲の人とともに、サポートしてくれる専門家に少し頼ってみることで、どうしていけばよいか、自分なりの答えがみつけられることがあります。