【何を知りたくて、どこが分からないのか】
わからないことはその場ですぐに医師に確認するようにしましょう。ただ、そのときは気にならず、後から疑問がでることもあります。どこがわからないのか、何について詳しく知りたいのかを整理して、次の外来時に確認しましょう。
質問の仕方は、自分のわからない内容、知りたい内容によって何通りもあります。
例えば「大丈夫という答えではよくわからないのですが、検査値は悪くなっていないでしょうか」と医師に質問して検査値を教えてもらったとします。けれども、その値の正常範囲や前回の値を知らなければ、問題はないのか、変化はないのかわかりません。もし、値が高い、あるいは低いなら、それはからだのどういうことを示しているのかを知る必要があります。
自分は何を知りたくて、どこがわからないのかということを考えて、わからないことは理解できるまで繰り返し質問してみましょう。

【治療に対して不安があれば納得・理解のために行動する】
治療方法や治療に伴うつらさなどへの不安や悩みがある場合、その根底には治療への理解が不十分であったり、未知の事柄への漠然とした不安があったりということがあります。
そこで、納得いくまで担当医にわからない点を確認したり、がんや治療方法について書かれた本を読んだり、インターネットで調べたりしてみましょう。
担当医に確認する際には、外来などでは時間も短いため、効率的に確認できるように、わからない点、もう一度説明してほしい点などを整理してメモ書きにしておき、そのメモを見ながら、あるいは担当医に渡しメモに沿って説明を聞くなどの工夫をしてみましょう。
インターネットや本で調べる際には、その情報が信頼できる情報かどうか気をつける必要があります。また、あらかじめ、自分のがんがどういう性質なのか、病期(病気の段階、ステージ)はどうなのかをよく理解した上で調べる必要があります。がんの性質や病期によって、適切な治療が異なる場合がありますので注意が必要です。

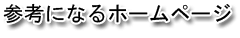 (1)国立がん研究センター『がん情報サービス』:病名からさがす https://ganjoho.jp/public/cancer/index.html いろいろながんに関する基礎知識、検査、治療、療養に関する情報があります。 (2)がん情報サイト :PDQ日本語版(米国国立がん研究所のがん情報サービス) https://cancerinfo.tri-kobe.org/ がん情報サイトには、『PDQ最新がん情報』、『PDQがん用語辞書』、『NCCNガイドライン日本語版』などの情報があります。 『PDQ最新がん情報』は、治療(成人、小児)、支持療法と緩和ケア、スクリーニング(診断と発見)、予防、遺伝学的情報、補完代替医療の情報があり、それぞれ『患者様向け』と『医療専門家向け』の2つのボタンがあり、より詳しい情報は『医療専門家向け』から得られます。 |
【あなた自身ができること】
あなた自身ができることをまず始めてみましょう
1. 『不安や不信』につながっている原因を自分の中で整理してみましょう。
まず、あなたが今不安に感じていること、疑問に思っていることを整理してみましょう。ノートに書き出してみても良いと思います。最初は、長い文章で自由に書いてみて構いませんが、書き終わったら読み直し、最終的に箇条書きにしてみると良いでしょう。たとえば、「○○の検査の結果が知りたい」、「○○という症状がどうして起こっているのか、知りたい。あるいは、どう対処したらよいか知りたい。」などです。ただ、先生ともっと話したいのに、忙しそうで話しかけられないとかではなく、具体的に整理することが大切です。
2. 予習・復習をしてみましょう
特に外来通院している場合、外来の診察時間は短いと感じ、担当医に確認しようと思ってもなかなか言い出せないという経験をお持ちの方もいらっしゃると思います。短い外来時間を有効に使うためにも、予習・復習をしてみましょう。
予習は、次の外来で実施予定の検査、あるいは結果の出ている検査、今ある症状や困っていること、担当医や看護師に聞きたいことを書き出し、整理してみることです。これは、できるだけ1行以内の箇条書きにして、間に空欄を入れておきます。この空欄は診察時や復習のときに使います。
復習は、診察室での診療のなかで、大切なことを自分なりに書き出して、まとめてみることです。その場では、すぐ聞けなかった疑問などがあったら、次の外来時に確認できるように、予習のところに、箇条書きで加えておきましょう。