【入院の期間】
近年は、在院日数の短縮化もあり、患者さんの心理的な回復が追いつかない、自宅の環境やご家族の協力体制が整わないなどの問題を解決する前に退院日を迎え、退院後に困ったり、心配事が生じたりする場合も見受けられます。
具体的な退院日時は、担当医の退院許可が出てから、相談して決定しますが、退院後の生活に困らないよう、あらかじめ身の回りのことや家事について検討しておく必要があります。生活の注意点に関して、担当医や看護師から話がありますので、ご家族と一緒に聞くとよいと思います。
また、ご自分の日常生活の一日をシミュレーションして、起こりうること、確認しておいた方が良い点をまず頭のなかで予習し整理しておくと、ご自分にあった注意点をきちんと確認できると思います。
【退院の時期】
担当医は、患者さんの状況に合わせて、医学的に退院しても問題ないという判断のもとに退院を決めていきます。ですから、退院してからも創(きず)の処置をしばらく続けなければいけないとしても、それは医学的には自宅で可能という判断に基づいたものです。創(きず)の観察ポイントや処置の方法を習得して、自己管理すれば、日常生活にほとんど支障はありません。
しかし、患者さんにとって創(きず)の処置などが残っている状態での退院は不安だと思います。
創(きず)の処置については、担当医や看護師から説明があります。ご家族にも一緒に聞いてもらえば、患者さんの状況がよく分かり、処置の手助けをしてもらったりするきっかけになると思います。
【ご家族と一緒に退院時の説明を聞くということ】
創(きず)の処置などの説明をご家族と一緒に聞くことのお話をしましたが、創(きず)の処置だけではなく、退院の際には、退院後の注意点や今後のスケジュールなどの説明は、できるだけご家族と一緒に聞きましょう。これは、創(きず)の処置のところでもふれましたが、一緒に聞くことでご家族に患者さんが今どういう状況であるかを知ってもらうことができます。もし、ご家族が仕事の都合などで、どうしても一緒に聞くことができないということであれば、担当医や担当看護師に申し出て、説明内容を録音しておき、後で聞いてもらってもよいと思います。
後で患者さんからご家族に伝えるからよいと考えられるかもしれませんが、患者さん自身、ご家族に心配や負担をかけないように一部しか話さない場合もあるかもしれませんし、患者さんから伝えると、そこに患者さんなりの理解や解釈が入ります。
ご家族と一緒に聞けば、後で情報交換して理解を確かめ合うことができます。
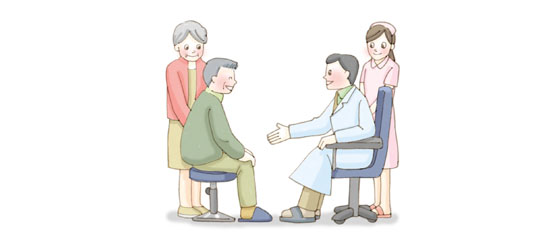
【退院後の日常生活はゆとりをもって】
退院したからといって、すぐに入院前のようにからだが動くわけではありません。手術の影響で、動きにくかったり、皮膚がつっぱった感じがあったり、痛みがあったりして、からだを動かすことにためらいを感じてしまうこともあるでしょう。その一方で、多くの患者さんは、家事やお子さんの世話、あるいは仕事のことなどの気がかりを抱えています。
がんと診断され手術などの治療を受けた後は、心許なさや再発の不安、様々な症状などでこころも不安定になりやすい状態です。最初は家事等も休みながら行い、一人では難しい部分や、疲れているときは、遠慮せずにご家族や周囲の人にサポートを求めましょう。一見、手術前と同じように見えても、手術をしたことで変化した部分も多く、周囲の方々はその変化に気づきにくいものです。
