患者さんから「入院中、同じ病気の患者さんに、これからの治療の話を聞いたり、アドバイスをもらって、少し安心した」という声を聞きます。
一方、外来では、診察時間が限られており、医師や看護師に気になっていることなどを十分に話ができないことがほとんどだと思います。
しかし、悩みは自分で抱え込まず、気になることを医師や看護師に質問してみましょう。患者さんの発言が診断の材料やきっかけになることもあります。
長い待ち時間のあいだ、患者さん同士のコミュニケーションがとれればよいですが、さまざまな病気、治療の段階の患者さんがおり、人の往来があり落ち着かない場所で、どの人なら快く応対してくれるのか、なかなか難しい状況です。
ご自分の病気の状態や行っている治療の方法・副作用・合併症などをよく理解することが、安心につながることも多いと思います。
相談窓口の利用
けれども、直接患者さんをみている担当医や看護師だからこそ、いえないこともあると思います。
その場合、相談窓口に話してみることも1つの方法です。
自分のかかっている医療機関に相談室があれば、そこに相談してみてもよいですし、各都道府県にあるがん診療連携拠点病院の相談支援センターでは、その医療機関にかかっている患者さんやご家族以外の相談にも対応しています。
患者会や患者支援団体のなかには、電話相談をおこなっているところもあります。
患者さん同士のコミュニケーションの場
悩み事を医療者に相談してみることも大切ですが、『患者さん同士だからこそわかりあえる悩みや気持ち』というものも確かにあります。また、直接、患者さんをみている担当医や看護師だからこそ、いえないこともあると思います。
患者さん同士の気持ちの分かち合いは、さまざまな形で行われています。たとえば、患者団体での集まり、あるいはソーシャルネットワーク、医療機関や地域の施設で開かれている『患者サロン(がんサロン)』、患者団体等が行う電話相談、いろいろな形ですが、同じような経験をした人たちだからこそ分かり合えるつらさや嬉しさ、思いがあります。地域内のこれらの情報に関しては、がん診療連携拠点病院のがん相談支援センターに尋ねてみましょう。
(更新日:2019年2月25日)
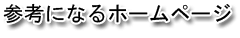 国立がん研究センター『がん情報サービス』:相談先を探す https://ganjoho.jp/public/index.html [相談先・病院をさがす]では、成人や小児の相談先・病院一覧(がん診療連携拠点病院、小児がん拠点病院)を病名や地域、病院の種類などから探すことができます。 |